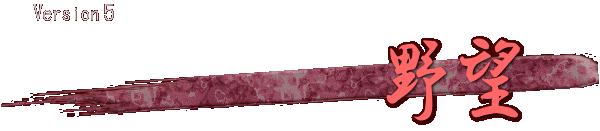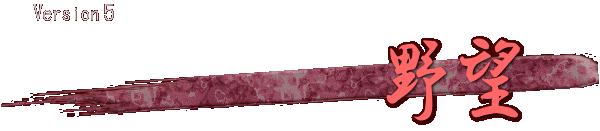中央公園の枯れた梢で、木枯らしが鳴った。
驚いて飛び立ったジョウビタキが、図書館の屋根を掠めて北へ向かう。冷気が風に乗って枯れた芝生を渡り、歩道に吹き上げてくる。
Mはコートの襟を立て、朝日を浴びた噴水を見つめ続けている。長い髪が寒風にもつれ、大きく見開いた瞳を被う。苛立たしく頭を振ると、襟足から寒い風が胸元に侵入した。乳首の先が冷気に震える。肩の力を抜いて、両手を握りしめた。端正な表情に疲労感が漂う。二十メートル先の、公園に下りる遊歩道にしっかりと視線を巡らす。寒い。
Mが見つめていた噴水の下に、一人の男が座り込んでいる。それも若い男だ。巨大な岩を削って作った、巨大なシャンペングラスのような噴水にもたれ掛かり、居眠りをしているように見える。表情はまるで少年のようだ。長い足を前に伸ばし、枯れきった芝生に座り込んだまま白々とした朝日を浴びている。
日光浴を楽しむには時間も早く、年も若すぎた。白い光を浴びた横顔に、暗い陰が浮かぶ。うなじを垂れ、目は伏せたままだ。グリーンのマウンテンパーカーのハンド・ウオマーに左手を突っ込んでいる。右手で握りしめたビニール袋が、日に反射して鋭くきらめいている。
Mの視線の中で反射光が微妙に揺れ、噴水にもたれた男の半身が大きく傾いだ。そのまま男は顔を左右に振り、半身の動きに任せて身を芝生に横たえてしまった。
力無く振られた男の顔に一瞬、媚びが浮かんだ。僅かに開かれた瞳が、目まぐるしく周囲を見回し、突き出た唇の先が言葉を紡ぐ。
「怖いよ」
Mは、はっとして息を呑み込む。頭の隅でスパークがきらめき、遠い過去の記憶が青い光となって甦った。
音もなく芝生に倒れ込んだ男の全身が、必死に救いを求めている。見つめるMの表情が厳しくなり、噴水に向かって足早に歩き出した。
記憶の底から聞こえてきた声は、子供の声だった。
六年前、冷たい坑道の闇の中から泣き声で呼び掛けてきた、気弱な少年の姿が脳裏に浮かぶ。
市の南を流れる水瀬川の上流の廃鉱となった鉱山の町で、一夏の間に繰り広げられたドラマに巻き込まれた三人の少年少女の姿が、遠い記憶の底に甦る。
「光男」
声に出して、少年の名を呼んだ。
あの年限りで廃校となった小学校の分校で、ことあるごとに泣き出しそうにしながら繊細な感性を育んできた光男は、中学校進学を機に市に転出した。幼い光男が心を寄せていた同級生の祐子と同じく、命門学院中等部に進学したのだ。その祐子にもMは、もう三年近く会っていない。そして少年たち。光男も、鉱山の町に一人残った修太も、別れてから六年になる。
押し寄せてくる思い出と、暗い予感に足を取られながら、Mは枯れた芝生を踏んで噴水へ急いだ。
Mが市に帰ってきたのは三年振りだった。しかし、三年前に比べ、市はほとんど変わり映えがしなかった。都会の喧噪に慣れた目には、灰色にくすんだ市街が惨めにさえ見えた。
深夜に都会を出て、高速道路を走り抜けた後、アクセスの悪い地方道を飽きるほど運転してきた。決して懐かしさを感じさせることもない市街を一巡し、官庁街に入ったところで、新しい公園を見付けた。車窓から見た銘板には、中央公園と書いてある。三年前には、コンクリートにひびの入った廃墟のようなスタジアムが建っていた場所だ。
確かな時の流れを感じさせる新しい建造物は、ドライブの疲れを癒すのにもってこいの場所に思われた。何よりも、三年前の記憶から遮断された風景が好ましかった。たとえ仕事で来たとはいえ、早すぎた到着を苦い思い出で飾りたくはなかった。
それが、三年前どころか、六年も前の記憶を甦らすことになってしまったのだ。
うんざりする疲労が寒さと混ざり、Mの足元から頭の先へ上がってくる。
寒々とした水を宙に吹き上げている噴水の下で、少年は身体を曲げて横たわっていた。
歩道から見た冷え冷えとした印象と異なり、そこは暖かな日溜まりになっている。枯れた芝生に横顔を当て、微かに息づく少年の表情に、Mは遠い日の面影を認めた。
光男に違いなかった。
「ミツオ」
小さく呼び掛けた声に、少年は反応しない。
横たわる少年の傍らに立ったMの影が長く、枯れきった芝生の先へ伸びている。
「ミツオ、起きなさい」
もう一度呼び掛けると、少年が微かに身体を震わせた。
「ウー」と低い呻き声をあげ、右手で握ったビニール袋をMに差し出す。
袋の中の白濁した液体が、朝日を浴びて輝き、怪しく揺れた。
異様な液体が邪悪な意志を伝える。Mは少年の横にしゃがみ込み、差し出されたビニール袋を素早く奪い取る。袋の口から透明の液体がこぼれ、Mの鼻孔を刺激臭が襲う。シンナーのにおいだった。
「ミツオ、ミツオ」
ビニール袋を投げ捨て、Mは二度名を呼んで肩を揺すった。周囲にシンナーの臭気が満ち、少年の鼻孔が膨らむ。
「フクロを返せ、クスリを返せ、」
ろれつの回らぬ口で、少年が訴える。大きく開かれた焦点の定まらぬ目で、不安そうに周囲を探る。
「ダメ、ミツオ。しっかりしなさい」
呼び掛けながら、Mは少年の肩を揺すり続ける。落ちそうになる頭が力無く揺れ、突然、少年の表情が戻った。憎悪に燃えた視線が、Mの目を突き刺す。
「ウルセイ、ババア。あっちに行け」
怒声が耳を打ったが、頼りないほど情けない声だ。
自分の声で覚醒した少年の目が、おどおどと周囲を見回す。探るような視線が二回、Mの目を掠めてから、足下へ落ちた。
堪らない悲しみがMの胸に込み上げてくる。憐憫といってもよかったかもしれない。
「私はM。ミツオ、もう私を忘れてしまったの」
顔を伏せたまま、しばらく間を置いてから少年が首を横に振った。
「ミツオ、私を見なさい」
できるだけ普通の声を出そうとしたが、M自身にも優しすぎる声に聞こえた。
Mの呼び掛けに、少年は反射的に顔を上げる。血走った大きな瞳の縁に、うっすらと涙が浮かんでいる。
「M、」
全身から声を吹き出させるようにして叫び、光男はMに縋り付く。勢いにバランスを崩し、Mも一緒に倒れ込む。
「M、M、」
呻くように、喘ぐように、光男は声に出して名を呼び、倒れたMの身体を撫で回す。
Mの目の前に、涙で濡れた光男の顔があった。大きく見開いた目から、止めどなく涙が溢れている。瞳の奥に、小さく身体を丸めてMをうかがう少年が見える。幼かった頃そのままに、全身で救いを求めていた。
Mは身体の力を抜き、光男の顔に頬を寄せた。冷たい涙の跡がMの頬を濡らす。頬をずらし、目元に唇を当てる。目の縁に舌を這わすと、よどんだ海の味がした。シンナーの刺激臭がまた、鼻孔を打った。
「しょうがない子ね」
耳元でささやくと「ウー」と尾を引いた嗚咽が洩れ、光男の全身が小刻みに震えた。
ひとしきり泣き続けた光男は、シンナーの酔いから急速に立ち直ってくる。
あっけないほど落ち着いた声が、Mの耳を打つ。
「ごめんなさい、M。ひどい姿を見せてしまった。僕を嫌いになった」
余りにも早い回復振りにMは戸惑う。しかし、素知らぬ顔で右肘を芝生に立てて、半身を起こした。
頭を芝生に寝かせたまま、顔だけMに向けた光男を見下ろし、優しく笑い掛ける。
「六年経っても、光男は変わらないわね。びっくりはしたけれど、嫌いにはならない。だって、あなたは病気なんだから。一緒に病院に行ってやるわ」
「そう。Mも病院に行ってくれるの。うれしいな。実は僕、夕べ遅く病院へ行ったんだ。でも、研修に行っていて留守なんだよ。仕方なく、ここでシンナーを吸って野宿することになっちゃった」
Mには光男の言うことが理解できない。病院を勧めたら、もう通っているような口振りをする。誰かが留守のため、寒い公園で夜を明かしてシンナーを吸っていたのだと言う。不可解すぎる言動だった。まだ、シンナーの幻覚が続いているのかもしれなかった。
「ねえ、光男。あなたの言うことは、よく分からないわ。掛かり付けの病院があるってこと」
「そう。市民病院のピアニストと友達なんだ。ピアニストは麻酔科医。でも、学位を取るために都会に通っているから、留守の日もある。夕べはたまたまその日にぶつかって、薬がもらえなかったんだ。薬がないと怖くて、とても眠れない。駅前で外国人からシンナーが買えてよかったよ。お陰で眠れたけど、Mに見付かってしまった」
今度はMにも意味が分かった。分かったどころではなく、ピアニストの消息も知れた。何となくいかがわしくはあったが、市民病院の勤務医になり、学位取得を目指しているらしい。その点では文句はなかった。
「学校はどうしているの。光男は命門学院の高等部でしょう。確か祐子と一緒なんじゃない」
「そう。僕は休学しているけど、祐子は三年生」
休学という言葉が耳に残ったが、今さら事の顛末を聞く気にはなれない。恐らく、光男の精神の状態に起因しているらしいことは、これまでの話しぶりから推測できた。
「祐子とは会っているの。六年生のとき、好きだったんでしょう」
「祐子はまぶしすぎる」
特に感慨もないように光男が言い切る。話題は病院に戻るしかない。もうすぐ外来も始まるはずだと思い、汚れた顔をのぞき込んで光男を促す。
「さあ、行きましょう」
呼び掛けに答えもせず、光男は横になったままじっとMを見つめている。
「Mはどうしてここへ来たの」
改めてMの存在を疑うかのように、不安そうな声で尋ねる。
「私は都会から車で出掛けて、今着いたところよ。新しくできた公園を見学していたら、この寒いのに日向ぼっこをしている、変な少年を見付けたってわけ」
「今も広告会社にいるの」
光男たちの住む鉱山の町へは、広告の仕事で行ったのだった。六年も前の仕事を、よく光男は覚えているとMは思った。もう、遠い過去のことだ。既に何回も職を変わっている。煩わしいくらいだった。
「広告会社にはいないわ。都会にある福祉関係の特殊法人で、機関誌の編集をしているの。今日は高齢者福祉特集号の取材で来たのよ。光男はコスモス事業団って知ってる」
「知ってるよ。ピアニストの病院もコスモスが持っているって聞いたことがある」
「でも、市立病院なんでしょう」
「詳しいことは知らないよ。市が病院を借りているって話さ」
光男の言葉でMは、事前調査の資料を思い浮かべた。確か、コスモス事業団のパンフレットで「在宅高齢者の訪問医療にも効率的に力を入れていく」と、理事長が抱負を述べていたようだ。光男の暮らしぶりも気になったが、Mは早くコスモス事業団の取材に手を着けたかった。三年振りの市は、早々とMに疲労を強いるように思える。
もう私は若くはないとMは思う。年が明ければ三十五歳になる。二時間の運転でさえうんざりしてしまった。たとえ懐かしい光男だろうが、立ち入らないで済む問題なら、そのまま済ましたい心境だった。
「さあ、病院に行きましょう」
気分を変えるように、勢いよく立ち上がったMが、光男に手を伸ばして言った。促されるまま返された光男の右手を握り、力いっぱい手元に引く。女のように細い手首が、今にも折れそうだ。
「痛いよ」
泣き声で訴える光男の横に屈み込み、片手で肩を抱いた。
ゆっくり抱き起こすと、足下をふらつかせて光男が立ち上がる。そのまま脇に手を回して二人で歩き始める。光男の身長は百七十センチメートルほどだ。肩も、ウエストも、スリムというより華奢といってよいほど脆く感じられる。
「スポーツはしないの」
ふらつく歩みが惨めに思え、Mが尋ねた。
「そんなもの嫌いだ」
「何が好きなの」
にべもなく言い切った光男に、反射的に問い返した。
「独りでいるとき。ピアニストといるとき。そして、Mといるとき」
甘えきった幼児が、身体を支えられてヨチヨチと歩いているのだ。Mには他に理解の仕様がなかった。子供のままでいたい少年にとって、構ってくれる大人は皆保護者に見えるのだ。肉親が注ぐような思いやりは、決して光男のためにはならないだろうとMは思った。十年後も少年でいられる道理はないのだ。
Mは口をつぐんだまま光男を支え、遊歩道を上って歩道に出た。
「さあ、乗りなさい」
歩道の縁石に沿って止めてある、オープンにしたホンダ・ビートのドアを開ける。狭い車内に窮屈そうに収まった光男を確認してから、運転席に回った。
「ずいぶん小さい車に替えたんだね。前のスポーツカーの方が似合っていたよ。Mも大変なんだね」
Mが運転席に座ると同時に、光男が言った。鉱山の町で乗り回していたロードスターと比べられたのだ。おまけに、経済状態まで推し量っている。まったく自分勝手な子供のままだと思ってしまう。
「都会では小さな車の方が便利なのよ」
答えながら思い切りアクセルを踏んだ。かん高いエンジン音の割には、期待していた加速感がない。やはり田舎では大きい車がいいとMも思った。
「いつまでいるの」
フロントガラス越しに巻き込む冷たい風に乗って、光男の問いが流れた。
「一週間の予定よ」
Mの声が、十二月の街に響き渡った。 |