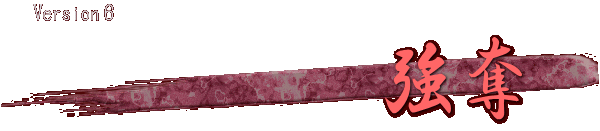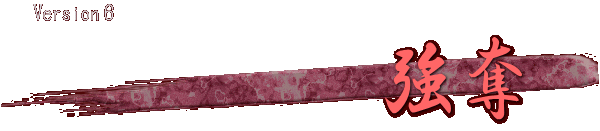仮眠室の電話が大きな音で鳴った。オレンジ色の常夜灯の光に包まれた狭い部屋で、Mは素早くベッド脇の受話器に手を伸ばす。当直の専務の声が耳に響いた。心なしか遠慮がちな声に聞こえる。
「仕事よ。M、」
呼び掛けた声がいつもの歯切れ良い言葉に繋がらず、少しの間が空いた。きっと煩わしい仕事に違いないとMは直感する。
「Mは、市に詳しかったはずよね」
深夜の専務は遠回しな物言いで話を続けた。Mは三十五歳の女性経営者の遠慮を感じた。同性の年長者への配慮だろうが疎ましくなる。
「ええ、詳しいわ」
都会から百キロメートル先にある、山と川に囲まれた地方都市の景観を思い出しながら正直に答えた。
「市で仕事をして欲しいの。市出身のH・I・Vの患者が亡くなったので移送して欲しいと、提携先の大学病院から連絡があったの。葬儀も併せて依頼すると言っているわ。故人の帰省先の希望なんですって。悪いけどMにお願いしたいの」
Mの勤める葬儀社では、遺体の移送は男性社員の仕事だった。それも深夜の移送だ。しかし今夜、五人いる男性社員はすべて出払っていた。社に詰めているのは専務の他はMしかいない。葬儀社の看板を掲げている以上、手に余る仕事でも断るわけにいかない。一度病院の信頼が損なわれれば、それまでの仕事だった。競争相手はいくらでもいる。
「いいわ、私が行きます」
「助かったわ。Mに断られたら私が行こうと思っていたの。正月早々、エイズ患者の遺体と地方出張だものね。男性社員だっていい顔はしないわ。すぐ事務所に来てちょうだい。病院が急いでいるのよ」
Mは受話器を置いてベッドから起き上がった。剥き出しの上半身を一月の冷気が襲う。両の乳首がキュッと締まった。全身に力を入れて思い切って立ち上がる。豊かな乳房が大きく揺れ、尻の筋肉が引き締まった。長い足が不安定なベッドの上でバランスを取り損ね、裸身が右に傾く。左足を横に踏み広げてかろうじて身体を支えた。大きく開いた股間で黒々とした陰毛が常夜灯の光を浴びて輝いている。Mは慎重にベッドを下りた。情けないほど肉体の重さを感じてしまう。特に胸と尻が心に重い。ダイエットなどをする気は毛頭ないが、これまで生きてきた年輪の重みが身体にこびり付いているような気がする。今年はもう四十歳になるのだ。素っ裸で眠る習慣にいつまで自意識が耐えられるだろうかと思い、頭を左右に振る。長い髪が大きく揺れて、足元から冷気が這い上がってきた。
二階の仮眠室から階下の事務室へ続く狭い階段の途中で、Mは左手に巻いたタイメックスのリスト・ウオッチを見た。ほの暗い空間で、燐光に浮かぶ文字盤が午前二時に近いことを知らせている。人の死に伴う儀式の影で働くMにとって、地味でさり気ないこの時計は必需品だった。服は黒いタートルネックのセーターの上にダークグレーのスーツ。長めのスカートから黒のストッキングに覆われた足が伸び、艶消しの黒いローヒールに続いている。右手に提げた出張用のスーツケースが重い。事務室のドアを開けると、スチール製の事務机を前にした専務が顔を上げた。デスクライトの光を浴びた疲れ切った目で、Mの全身を点検するように見た。
「ご苦労様。相変わらず支度が早いわね。セーターよりブラウスの方がいいけど寒いからね。きっと百キロメートル先の市も寒いでしょう。これが故人の資料。悪いけれど古い方の寝台車を使ってちょうだい。大きいから荷物が積めるわ。Mが来る前に帰省先と連絡が取れたの。無宗教だと言っていたわ。簡単な祭壇だけ積んでいって。それからお棺も一緒にね」
必要なことだけ口早に言った専務は、フォルダーに留めた書類をデスク越しに差し出してからランプシェードを上げた。Mはスーツケースを床に下ろし、受け取った書類に目を通す。癖のある文字で必要事項が記入されている。Mの視線が書類の一点で止まった。フォルダーを持つ右手が微かに震え、両肩がしばし緊張した後、静かに肩が落ちた。大きく見開いた目から涙がこぼれ、頬を伝って紙片に落ちた。白い紙面に書かれた光男の名を涙が濡らす。
Mは懸命に四年前に別れたきりの光男の姿を思い描こうとした。だが、頭も心も真っ白なままで何の像も浮かび上がろうとしない。雑然として暗い都会の雑踏だけが、頻りに頭の隅をよぎっていった。Mの暮らすこの都会のどこかに光男は移り住み、どれほどかの喜びと悲しみを残してエイズで死んだのだ。真っ白な悲しみがMの全身を覆いつくした。
「どうしたのM、涙なんて流して。ひょっとして故人と知り合いなの。私が代わりに行ってもいいのよ」
涙に霞む目に当惑した専務の顔が映った。事情を話し、専務に代わってもらった方がいいと、冷たく覚めた理性の声がMに告げる。だが声に抗うように、はっきりした言葉が口を突く。
「いいえ、これは私の仕事です」
答えを聞いた専務の顔が更に当惑する。Mの言う仕事の意味がよく捕らえられないのだ。
「確かに故人は私の知人です。でも、私情で仕事はしません。立派な仕事をすることが故人への義務ですものね」
込み上げてくる嗚咽を抑えてMが答えた。
「そう、それほど言うなら予定通りお願いするわ。知り合いがエイズで死ぬなんてショックでしょうね。伝染の怖れもあるし」
「専務、私は闇雲にエイズを恐れてはいない。エイズは感染力の弱い病気です。血液をとおしてしか感染しない」
苛立った声に専務がまた当惑した。
「Mの言う通りね。でも、長い間記者をしていたMと違って、普通の人はエイズに恐怖感があるわ。治療法がないんだものね。確実に死ぬことが分かっている病気はやはり怖い。どうしてMは、記者を辞めてうちに来たの」
とんだところでMは職歴を問われた。人手不足の葬儀社で初めて発せられた問いだった。
「私は転々と職を変えただけで記者をしていたわけではないわ。二年前にここに勤めたのは、給料が良かったから。早速仕事にかかります」
涙で濡れた書類をショルダーバッグに入れてからMが答えた。今さら死者が身近に感じられてきたから転職したと言って、数度目の当惑を専務に感じさせる必要はなかった。
「気を付けて行って来て。これは宿泊費。領収書を忘れないでね」
経営者の顔に戻った専務が金の入った封筒と寝台車の鍵を差し出す。
「行って来ます」
Mの声が深夜の事務室に響いた。
寒そうに星が瞬く夜道を、Mは駐車場へ急いだ。胸を張って大股に歩くが、怒らせた肩が啜り泣きに震える。古ぼけたプレハブ造りの駐車場の前まで来て、大きく息をついた。くずおれてしまいそうになる腰に力を込め、重い鉄扉を小さく開いた。底冷えのする闇が全身を覆う。手探りで壁のスイッチを押すと、高い天井に蛍光灯が灯った。ぼんやりした青い光が巨大な霊柩車と寝台車を照らしだす。Mはマイクロバスほどの大きさがある黒塗りの寝台車の後ろに回った。古ぼけた観音開きの後部ドアを開けて、積んであった折り畳み式の担送車を降ろす。死者を乗せる広々としたスペースに、葬儀に必要な機材を積み込まねばならない。まずガレージの隅に置いてある簡易型の祭壇のコンテナを奥に積み、続いて棺を積み込む。止まっていた涙がこぼれ落ち、白木の棺を濡らした。最後に、降ろしておいた担送車を苦労して棺の横に入れた。死者を包み込む白布が付いたマットをロッカーから出し、そっと担送車の上に載せた。この白いマットに死んだ光男が横たわるのだ。狭苦しい車内の光景が再び涙を誘った。正面のシャッターを大きく開き、寝台車のエンジンをかける。Mはようやく落ち着きを取り戻した。
静まり返った深夜の都会を、漆黒の棺車が光男の遺体を迎えに急ぐ。黒々とそびえる大学病院の古い建物の影を縫うようにして、Mは地階の駐車場入口へ回り込んだ。死者が退院する場所は地下の裏口と決まっているのだ。不可解な病院の定めだった。物に変わってしまった患者に人は冷たいとMは思う。警備員に事情を話し、病棟に向かう許可をもらう。担送車を降ろし白いマスクをする。胸ポケットの上に身分を証明するカードを付けてから、担送車を押して院内へと進んでいった。打ちっ放しのコンクリートの壁に挟まれた迷路のような通路を何度か曲がって、エレベーターの前に出た。コールボタンを押すと、静まり返った通路にエレベーターの下りてくる音が低く響いた。担送車専用の広々としたエレベーターに乗り込み、書類に書かれてあった四階のボタンを押す。再び扉が開くと、病棟を照らす常夜灯のほのかな光がMを迎えた。並んだ病室の間に担送車の車輪の音が響き渡る。
「イタイ、クルシイ、ハヤクコロセ、」
静まり返った病室の奥から苦痛に啜り泣く患者の声が聞こえてきた。押し殺した喘ぎ声が、耐え難い痛みをMに伝える。廊下の中程まで進むと、明るく照らしだされた医局の窓が見えた。年配の看護婦が急ぎ足で出て来る。
「遅いじゃない。それに一人なの」
「済みません」
小さな声で言って頭を下げた。看護婦が眉を寄せ、Mをにらんだ。気まずい雰囲気が満ちる前に、若い医師と幼さの残る看護婦が医局から出て来た。
「これが死亡診断書、確実に家族に渡すこと、いいね。葬儀社の人だけだと困るんだが、遺体の引き取り手が医師なので了承します。さあ急ごう」
医師が差し出す封筒をポケットに入れ、Mは黙って三人に従う。病棟の一番奥まったところにある六人部屋の前で一行は止まった。
「満室だから、できるだけ静かに」
声を落としてMに言った医師が両手にゴム手袋をはめる。二人の看護婦が医師に倣って手袋を出した。
「君は手袋を持ってきたかい。H・I・Vの患者だって言ってあったろう」
責めるように医師が言った。
「私は手に傷がないから要りません」
即座にMが答えた。小さくうなずいた医師が先に立って病室に入った。懐中電灯を肩から背負った二人の看護婦が後に続く。Mは廊下で担送車の向きを変え、後ろ向きに曳きながら病室に入っていった。部屋の両側に三つずつベッドが並び、入口から延びた通路はやっと担送車の幅しかない。狭い室内は暗い。白いカーテンで仕切られた五つのベッドで、患者たちが息を殺して長い夜を耐えていた。右側の奥のベッドで懐中電灯の光が揺れている。この病室で一人だけ永い眠りについた光男がMを待っているのだ。
Mは担送車を窓際につけ、載せてきたマットの頭の部分を持った。慣れた手つきで年配の看護婦が足の部分を持つ。ベッドの端に寄せられた光男の床に二人でそっとマットを下ろす。医師が光男の頭を抱え、二人の看護婦が胴を支えた。Mは細い腿を支え、四人で共同してマットの上に遺体を乗せる。軽々とした光男の重さが、まだ温もりの残る肌の感触とともに両手に伝わってきた。遺体を移動させたことで、一応の任務を終えた医師と看護婦が前後して身体を引いた。マットに備え付けた白布で遺体を覆うのはMの仕事だ。目の下に光男が横たわっている。ほっそりとした顔はきれいに整えられ、閉じられた目がMに会うことを拒否している。赤く染めた髪は乱れ、右の耳で金のピアスが光っていた。骨と皮だけになった細い両手が祈りを上げるように胸の上で合わせられ、白い包帯で手首を結わえてあった。今さら何を祈ろうと言うのか。Mの目に涙が浮かび、止めどなく流れ落ちた。涙は白いマスクに次々と吸い取られていく。声も出さずにMは忍び泣いた。
Mの様子を怪しんだ医師が素早く身を乗り出し、ファスナーの付いた白布で遺体を覆う。Mの気持ちなど構わず、光男の顔を白布で包み終わると非情にファスナーを上げた。涙に霞む目で見下ろす光男は、まるで粗大ごみのように白い袋に入れられてしまった。医師が看護婦たちに目配せし、三人でマットの取っ手をつかんだ。目の前で光男の身体が斜めに浮き上がる。慌ててMも足元の取っ手をつかんだ。マットに横たわり白布で覆われた遺体が何回か宙で揺れ、軽々と担送車に収まった。それでいっさいが終わった。Mは黙ったまま担送車を押し、暗い廊下を再びエレベータへ向かう。送ってきた医師と看護婦が遺体に頭を下げた。エレベーターの扉が締まると、明るい方形の箱の中にMと光男だけが残った。Mは光男を覆った白布を開きたくなる衝動を抑え、声を上げて泣きじゃくった。ひたすら力を込めて担送車を押し、元来た道を戻って、駐車場に帰り着いたときは、全身がぼろ布になったように疲れ切ってしまった。このまま逃げ出してしまいたいという思いが何度となく込み上げてきたが、見たばかりの安らかな死に顔がかろうじてMを引き留めた。人気のない病院の地下駐車場の冷気がMと遺体を包み込む。
「怖いよ、寒いよ、M、助けて」
甘ったれた声の記憶がMの耳に甦る。鉱山の町の真っ暗な坑道で十二歳の光男が泣く。そして十八歳の光男が、鋸屋根工場の北向きの光を浴びて啜り泣く。痛々しいくらい貧弱な裸身が救いを求めて震えている。
「ワッー」
駐車する車両も疎らな暗い地下駐車場にMの叫びが響き渡った。もう悲しみの奔流を押し止めることはできなかった。ダークグレーのスーツを脱ぎ、黒のセーターをむしり取った。スカートを脱ぎ、ストッキングを剥ぎ取る。素っ裸の胸で乳房が震え、広げた股間で固く突き立った性器がおののいた。担送車の上のマットに両手を伸ばし、遺体を覆った白布のファスナーを下ろした。今にも目を開きそうな邪気のない死に顔が目を閉じたままMをうかがっている。胸の上で両手を組んだ痩せ細った光男の身体を、そっと素肌で覆った。温かな裸身に触れる、冷えていく肉体の感触が悲しい。Mは光男の体温を甦らそうとするかのように、冷え切った頬に頬を擦り寄せ続けた。突然、白い裸身を懐中電灯の光が照らしだした。
「汚れない仏に何てことをするんだ」
紺色の制服に身を包んだ初老の警備員が、全身を怒りで震わしながら鋭い声で叱責した。端正な顔を苦悩に歪めたMが遺体から身体を離し、豊かな裸身を大きく上に伸ばした。静かな声が冷気を揺るがす。
「かわいそうな弟の弔いを邪魔しないで欲しい」
懐中電灯の光が一瞬揺れてから消え、足音が去っていった。薄暗い駐車場に白々とした裸身だけが立ちつくす。 |