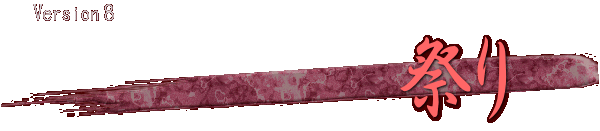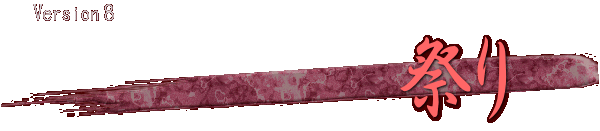肌に粘り着いてくる暑い湿気が朝の微睡みを不快にさせる。
寝汗にまみれた綿毛布を床に落とし、Mはベッドで寝返りを打った。大柄な裸身が青いシーツの上で緩慢に回転する。カーテン越しに差し込む光が汗ばんだ肌を白々と照らしだした。深い尻の割れ目になまめかしい陰影が浮かぶ。
部屋の窓は北に面している。南側に玄関がある不思議な造りのワンルームのアパートだった。もっとも、南隣には軒を接するようにして四階建ての医院があった。後から建てられた二階建ての木造アパートにしてみれば、どうしようもない間取りといえた。
Mがこのアパートに移り住んでから、もう三年になる。金貸しの老人の殺人事件を機に、遊郭跡のアパート富士見荘から仕方なく引っ越してきたのだ。家主が犯人として逮捕された以上、木造三階立ての元遊郭も最後の命運が尽きたといってよかった。取り壊される運命の富士見荘に残された、三人の老婆の身の振り方を考えるのはケースワーカーの天田の仕事だった。だが、Mの身の振り方まで天田に考えさせるわけにはいかない。Mは勤務先の警備会社の交通業務主任の紹介で月五万円のこのアパートに転居した。家賃は約十倍になってしまったが、入社六か月で正社員になれたMには住宅手当がついた。その後、警備会社が新たに始めた総合人材派遣部門を担当して二年が過ぎ、今や手取り二十五万円の派遣業務主任だった。極めて普通の生活が続いているといってよかった。
しかし、今もって市にいることを、折に触れてMは疑問に思う。ピアニストの自殺によって、戸籍上の未亡人になったときに市を去るべきだったと悔やむこともある。結局、求められれば応じるのがMの生き方だった。祐子が、チーフが、そして警備会社も、ピアニストの父の歯科医さえMを求めた。何にも増して睦月の愛憎がMを放さなかった。修太を殺したと言いつのり、ことあるごとに睦月はMを責めた。睦月の説の半分は認めざるを得ないMには、修太の子の進太の成長を見守る義務もあった。それがピアニストの妻の役割にも思える。少なくとも、自分の死で現金強奪事件と修太を始めとした十二人の死に責任を取ろうとしたピアニストの意志は尊重したかった。
Mは仕方なく、歯科医に請われるままピアニストの遺産を相続することにした。弁護士に言われたとおり書類にサインし押印しただけで、今もって財産がどれほどあるか知らない。預貯金に手をつける気さえない。書類はすべて祐子に預けてしまった。コスモス事業団の理事長の遺産を相続していた祐子が、管理者として適任だと思えたのだ。遅れて刑務所を出所してくる極月や霜月を迎える心配も、ピアニストの妻の仕事に思えた。二人とも帰るところなどあるはずがない。同じ傷を負った者同士が、ひっそり寄り添うしかない。幸い、蕩児の帰郷に市は極めて寛大なのだ。これまでのMと睦月の暮らしがすべてを証明している。ピアニストにまつわる一切のしがらみがMをこの市に縛り付けていた。一人で都会に逃げ帰るわけにはいかない。三年間は瞬く間だった。
目覚まし時計の耳障りな電子音が響いた。
Mは手を伸ばしてサイドテーブルに置いた時計のベルを止める。ついでにエアコンのリモートコントロール・スイッチを入れた。窓の上に取り付けたエアコンが静かな唸り声を上げ、蒸し暑い部屋の空気を追い払っていく。素肌に浮いた汗が瞬く間に消え去っていった。
肌の冷えを感じるまで待って、Mは起き上がった。真っ先にカーテンを開ける。今にも降り出しそうな分厚く垂れ下がった梅雨空の下に水道山の緑が広がっている。北向きの窓だが、心が落ち着く景観だった。
山の中腹のこんもりとした森陰に鮮やかな黄色の屋根と青い屋根が見える。青い屋根は像舎で、黄色のほうはキリン舎の屋根だ。どちらも市が近隣に誇る市立動物園の人気者だった。特に二年前に来たキリンは子供の夢を刺激し続けている。小学校の一年生になったばかりの進太も例外ではない。入学する前は毎日欠かさずキリンに会いに行くのが習慣だった。今は日曜日の度に出掛けている。昼近くならなければ起きない睦月の目を盗んで、進太は毎週動物園に通い続けていた。キリンと会った後は、決まってMの部屋を訪ねて来たが、これも睦月には内緒だった。もうじきノックもせずに進太が訪れ、心ゆくまで遊んでいくはずだった。ベッドから起き出したMが裸でも、進太は何の頓着もしない。まさに傍若無人な子供だった。それもMや祐子、チーフの前だけで、母の睦月といるときはおどおどとした振る舞いが目立った。進太は睦月の体罰が怖くて仕方ないのだ。進太を取り巻く大人たちにとっては周知のことだった。睦月は誰の目の前でも遠慮なく進太を折檻した。母子だけのときは生命に関わるほど責めるに違いない。折檻と言うより虐待と言った方が近い。進太の身体にはいつも生傷が絶えない。皆が眉をしかめていたが、誰も睦月に意見することができなかった。興奮した睦月が、それこそ進太を殺しかねないと危惧していたからだ。睦月はしつけのための愛の鞭と言って憚らなかった。Mは睦月のアパートと五百メートルも離れていない部屋を選んだことを悔やむ。でも、進太の逃避先と思えば諦めがついた。しばらくぶりに、進太を動物園に迎えにいってやろうと思う。今日は午後から人材の派遣先と、新たな事業の打ち合わせをするために会社に行く予定だった。新しい仕事は幸い忙しかった。休日出勤を前に、進太と他愛ない時間を過ごすのも楽しそうな気がした。
Mは窓のカーテンを閉め、ユニットバスに向かった。小さなバスとトイレ、洗面台が備え付けになった玄関脇の一角で顔を洗う。冷たい水が気持ちよい。睦月が進太に与える虐待の記憶を吹き飛ばそうと、思い切って水を使う。素肌に飛沫が跳ぶが、水滴をはじき飛ばす皮膚の張りが失われたことが寂しくなる。四十五歳の素顔が正面の鏡に映っていた。
進太はいつものように正門の職員通用口から園内に入った。幼いころから動物園に入り浸りだった進太は、すべての飼育員と顔見知りだ。誰にも見咎められることはない。開園前でも朝の動物園はにぎやかだ。餌を求めて鳴き交わす動物の声が、山麓を切り開いた園内に響き渡る。
進太はコンクリートの壁の上で、フェンスに背をもたれさせて座っていた。垂らした足の四メートル下にキリン舎の運動場が広がっている。
「サクタロウ、おいで」
真向かいの砂地に並んで立った三頭のキリンに進太が呼び掛けた。しばらく前に家族の元に帰っていた特別大きいサクタロウが声に応じ、ゆっくりと向きを変えて進太の方に歩いて来る。サクタロウは網目キリンの雄で、キサラギの夫でキリタロウの父だ。父になってまだ半年しか経っていないためか、子供の進太にも頼りない動きに見える。ただ背はあきれるほど高い。長い首を伸ばし、巨大な顔を四メートル上にいる進太に近付けてきた。いたずらそうな黒い目で進太を見つめながら、もぐもぐと口を動かして目の前まで顔を寄せる。不意に長い舌を伸ばし、膝に置いた進太の手を舐めた。温かいヤスリを手に当てられたようなざらついた感触が心地よい。多量の涎で手がぐしょ濡れになる。
「ダメッ」
進太が怖い顔で言うと、さっと首を上げて大きな目で見つめた。邪気のない目がかわいくてならない。進太はサクタロウの唾液で濡れた手を背中に回し、フェンスの下に茂った草を抜き取る。相変わらずもぐもぐと口を動かして食物の反芻を続けているサクタロウの目が進太の動作を捉えて輝く。すっと長い首を伸ばし、進太の手を追う。意地悪くサクタロウの目の前で草を振ってみるが、進太の上半身ほどある顔と口の前では空しい。瞬く間に草の束はサクタロウの口の中に消えた。すぐ後ろで様子を見ていたキリタロウが父の真似をしようとするが、子キリンでは壁の半分の高さまでしか首がとどかない。母のキサラギがとがめるように見つめている。キリンの一家でも母は怖いのかと進太は思う。でもキリタロウには、子供のようで頼りないが父のサクタロウがついている。母のキサラギも折檻できないに違いないと思って羨ましくなる。
草を噛んでいたサクタロウが首を曲げ、進太の膝に巨大なあごを載せた。剥き出しの腿が針で突かれたように痛い。昨夜、ママに物差しで打たれたばかりの、赤く腫れ上がった痣が飛び上がるほど痛んだ。キリンの毛は短く、歯ブラシのように固いのだ。皮膚はぱんぱんに張り切っていて、まるでブラシの毛を植え付けた大太鼓のようだ。
「サクタロウ、僕を背中に乗せてよ」
進太はサクタロウのあごを撫でながら真剣な声で頼んだ。声を聞いたサクタロウが首を上げ、少し離れて訝しそうに進太を見る。
「サクタロウ、乗せて」
また進太が頼んだ。サクタロウが笑う。笑ったように進太には見えた。さっと巨体を翻し、狭い運動場の端に向かって軽やかに駆ける。蹄の音が静けさの中に響いた。黄色と黒の網目が目にまぶしく美しかった。
サクタロウの首に抱きつけなかったことを進太は今日も悔いた。たとえサクタロウが背中に乗せてくれず地面に転落したとしても、それがどうしたと痛切に思う。進太はきつく唇を噛みしめ、四メートル下の地面をじっと見つめた。胸の底に押し殺していた記憶がまた喉元まで込み上げてくる。まだ幼かったころ、ママは何度も僕を、胸の高さから布団の上に落としたのだ。泣き声もでなくなった僕を、ママは敷き布団の上に落とし続けた。恐ろしいほど真剣なママの目を今も覚えている。とてもキリンのように反芻したくはない圧殺したい記憶だった。今更転落が恐ろしいとは決して言わせないと自分を叱る。
真っ白になった進太の視界の隅で、そのとき黒い影が揺れた。数回まばたきをして進太は影を見つめる。上り坂になったキリン舎の正面の道をMが上ってくる。黒のTシャツにブラックジーンズを合わせたいつもの格好だった。身体の線が見て取れる姿が、進太の目にも美しく見える。歩みに連れて長い髪がふっくらと揺れた。進太の表情が一瞬に輝きだす。
「Mっ」
立ち上がって大声で叫び、両手を上げて左右に振った。途端にフェンスの向こうから飼育員の梅田さんの声が響く。
「進太、客が来る前にフェンスの外に出ろよ」
「はい」
明るい声で答え、進太は金網のフェンスをよじ上る。フェンスのてっぺんでキリン舎を見下ろすと、三頭のキリンがそろって進太を見上げていた。
「僕もパパが欲しいな」
アパートのドアを開けて玄関に入ると同時に、進太がMに言った。Mは面食らって進太の顔を見つめる。とっさに答えが見付からない。当たり前の話だ。父のいない子供が父を欲しがっている。Mに答えられる道理がなかった。
「サクタロウみたいな頼りないパパでいいんだ。パパさえいればママに叱られなくて済む」
Mの答えなど求める風情もなく興奮した口調で言って、進太は部屋の中に飛び込んでいった。
真っ先にキッチンに行き、冷蔵庫を開いてミルクと食パンを持ち出す。八畳の部屋に置いたテーブルの前に座り、牛乳パックから直接ミルクを飲む。細い喉が鳴り、唇の端から白いミルクがこぼれる。続けて食パンをモリモリと頬張る。
「トーストにして、バターを塗ってやろうか」
見かねてMが声を掛けるが、答える暇を惜しむかのようにパンを食べてはミルクを飲む。睦月の冷蔵庫は今朝も空に違いないと思い、Mは暗澹とした気持ちになる。一週間前に用立ててやった五万円を使い果たしてしまったに違いなかった。つい聞かなくてもよいことを聞きたくなる。
「進太、昨日の晩御飯は食べたの」
「抜きだよ。勉強しないでテレビを見ていたから、ママに叱られたんだ」
やっと人心地がついた様子の進太が、吐き捨てるように答えた。Mには睦月の子育て振りが残酷に見えてならない。だが、食べ物を買う金がないことを子供に告げるのと、子供の罪をとがめて絶食を命じるのと、どちらが子育てにかなっているのかMには判断できない。育児は各家庭の個性に属するものと言えた。
「M、甘い物が食べたいな。給食のデザートみたいなのでいいよ」
食べ散らかしたまま立ち上がった進太が、Mの答えも聞かずにキッチンに消える。自分の家では間違ってもするはずがない進太の振る舞いが、いつもMを戸惑わせる。睦月の厳格さとMの放任と、どちらが進太のためになるかを考えてしまう。当然、責任が無い分だけMの方が分が悪い。やはり進太の将来に渡って責任を負うのは睦月しかいない。それが進太を生んだ睦月の母としての務めに違いなかった。
「わーすごい、アップルパイがあったよ。全部食べていい」
キッチンから嬌声が聞こえ、進太がケーキの箱を持って戻ってきた。人材を派遣した先の会社社長が、お礼にと言って金曜日に持ってきたものだ。社員が十人ほどの情報サービス会社だが、時流に乗って手広く事業を広げていた。当然、理工系の基礎知識を持った人材を求めてきた。有能な調査員が欲しいという要求に応え、Mは思いきって刑務所を出所して半年になる極月を交通誘導部門から引き抜いて派遣した。つい一か月前のことだ。極月はコンピューター・システムの基礎調査員として、めざましい働きをしているという。極月の能力を持ってすれば、喜ばれるのも当たり前のことだった。今日の午後会うことになっているのは、水瀬産業というその会社の社長だった。久しぶりで極月に会えるかも知れないと思うと、つい口元がほころんでしまう。
肘掛け椅子に座って極月の仕事ぶりに思いを馳せたMにお構いなく、進太はアップルパイを丸ごと貪り始めていた。あまりの傍若無人振りに、つい注意をしたくなる。立ち上がろうと椅子を鳴らした途端、背中を見せて座り込んでいる進太がパイを噛みながら声を出した。
「ねえM、サクタロウはいつも食事をしているんだ。便利でいいよね。ひもじい思いをしなくて済む」
立ち上がり掛けたMは、また椅子に腰を下ろす。進太は背中に目があるのかと疑いたくなる。行儀の悪さを注意しようと思った気持ちが、ひもじさと聞いてつい不憫さに変わってしまう。何と言っても世は飽食の時代なのだ。今時小さい子供を抱えて冷蔵庫を空にしておく家庭など考えもつかない。
「ねえM、聞いてる。サクタロウは僕を背中に乗せてくれるかも知れないんだ。そうしたら、僕は一緒にアフリカまで旅にでる。サクタロウがいればママなんて要らない」
進太は返事に困ることばかり言う。いつものことだった。Mと会話をするのではなく、一方的にしゃべりまくり食べまくる。食べ終わった後は決まってテレビゲームを始める。もちろん睦月に内緒で買い与えたものだが、進太は怖くて家に持って帰れない。テレビに接続したままになっているゲーム機を持ち出し、掛け声をかけながらゲームに熱中する。Mのことなど眼中にないのかと思っていると、隙を突くように話し掛ける。
「M、なぜママはいつも裸でいるの。Mも裸でいることがあるけど、ママほどではないよね」
ゲームに熱中しながら、唐突に問い掛けた今朝の問いも珍妙だった。Mは頬を赤く染め、口を開けたまま絶句してしまった。
三年前にチーフが再開したクラブ・ペインクリニックで、睦月はSM自縛ショーを自作自演している。スナックのホステスではプライドが許さなかったようだ。クリエイテブな仕事をしたいと言うのが睦月の口癖だった。しかし、舞台の上で裸になり、自らを鞭打ったり滑車を使って天井から吊り下がってみたりするショーがクリエイテブだとは到底思えない。Mは睦月のショーを見たことがない。人の目も気にせず励む、ショーの練習を見せられるだけで十分だった。睦月がなぜSMを選んだのかMは知らない。恐らくSMショーの女優をしていたチーフの影響だと思うが、チーフにも睦月にも問いただしたことはない。Mの嫌ったクラブ・ペインクリニックを再開するからには、チーフにも相当の覚悟があったはずだった。チーフも三十八歳になる。サロン・ペインの経営者としての自負もあったと思う。結局、睦月は舞台に熱中した。今では前衛舞台のアーティストと思い込んでいる雰囲気すらある。新しいアイデアが浮かべば自宅でも、すぐ裸になって縄を持ち出し、自縛の稽古に余念がない。子供の進太の目を怖れる睦月ではなかった。進太が言うように、いつも睦月が裸でいるわけはないが、子供心には強烈な印象を与えるに違いなかった。それでも、幼いころから裸の睦月を見慣れた進太は、Mの裸にも頓着しない。たまたまMが裸でいるときも、平気でズカズカと部屋に入ってくるだけの話だった。むしろ羞恥心の育たない進太の成長に問題があると思う。
Mの心の動きを察したように、テレビの画面に見入っているとばかり思っていた進太が急に振り返った。真剣な表情でじっとMの目を見つめる。
「M、お願い。今ここで、僕に裸を見せて」
ボーイ・ソプラノで訴えた声が、Mには妙に大人びて聞こえた。もちろん返事につまる。
「私はママではないわ。裸で仕事はしない」
答えてしまってからMの心を悔いが走り抜ける。まるで職業蔑視を絵に描いた答えのように感じた。全身がかっと熱くなり顔が真っ赤になった。すかさず進太がMの長い足に絡みつく。
「ねえM。お願いだよ。Mはママと違うのはよく知っている。Mは夜の仕事はしないものね」
無邪気なのか、ませているのか判じかねるソプラノで訴え、椅子に座ったMの膝にのし掛かってくる。Mの頬が益々赤く染まる。子供見くびりを指摘されたような気さえした。もうMに勝ち目はなかった。進太が両手を身体の下に差し込み、Mのジーンズのボタンを外す。
「裸になってくれないなら、僕が脱がしちゃうぞ」
甘える声が耳をくすぐり、叱りつけるタイミングを失ったMのジーンズのファスナーが下ろされてしまった。
「今度だけよ」
我ながら陳腐に聞こえる言葉を口にしてから、Mは黒いTシャツを脱いだ。高く上がった豊かな乳房が進太の目の前で揺れる。進太は息を呑んで後ずさる。Mは静かに立ち上がってブラックジーンズを脱いだ。恥ずかしいところなどない裸身だが、子供の進太に穴の空くほど見つめられると、さすがに全身が羞恥で赤く染まった。高く切れ上がった股間で黒々とした陰毛が天を突く。
「わあー、Mはきれいだね。大きくていいよ。大きなお人形さんみたいだ。ママとは段違いだね」
感嘆の叫びを口にして、進太が胸に飛び付いてきた。素っ裸のMが進太を抱き留め、背中を抱く。ちょうど臍の所にきた進太の顔から温かな滴が湧き出し、Mの素肌を濡らした。進太が泣いているのだ。抱き締める腕に力がこもった。
「サクタロウと違って、Mの裸は柔らかで気持ちがいい」
啜り上げる声で進太が訴える。不吉な兆候だった。Mは進太を抱いた腕を解き、静かな声で言う。
「進太、ママの方が私より二十歳も若いのよ。ママの肌の方がずっと張りがあって柔らかいと思うわ」
「僕はママに抱かれたことはない」
怒った声で進太が叫んだ。続けてまた啜り泣く。Mの部屋で始めて見せる態度だった。Mの裸身が全身で戸惑う。
もしかしたら、とMは思い悩む。
進太は睦月とMの二人に、同時に母を見ているのかも知れなかった。そんな馬鹿なと、Mは浮かんできた考えを打ち捨てようとしたが、進太の心の中まで見ることはできない。これまで進太の逃避先だとばかり思ってきたMが母に変わる。Mの背筋を冷たい感触が走り抜けた。全身がわなわなと震えだしそうだった。その時、臍の辺りにあった進太の顔が急に下がった。小さな顔をMの股間に埋める。小さな手が両膝を押し開き、あごを持ち上げて口で股間をまさぐる。突き出た性器が強く吸われた。Mの高揚した気持ちが急速に静まっていった。やはり、進太は他人だったとつくづく思って安心する。小さくとも進太は立派な男だ。舌こそ使えないが、乳首を吸う要領で性器を吸い続けている。緊張の解けたMの股間が熱くなり、官能の火が灯る。陰部が濡れてくるのが分かった。きっと睦月も子供のままなのに違いないと、苦い思いが唐突に告げていった。
昼近くなると蒸し暑さがつのってきた。
Mはエアコンのスイッチを除湿から冷房に切り替えた。裸のままだが十分すぎるほど暑い。進太を意識するあまり、服を着るタイミングが今もって見いだせないでいた。まったく不器用だと思うが仕方がない。つくづく子供は苦手だと思うしかなかった。進太は満ち足りた顔でテレビゲームに戻っていた。小さな背中が時折震え、興奮した声が口から漏れる。子供が安心できる場所はゲームの中にしかないのかと思って空しくなる。
「アーア、また負けてしまった。M、お腹が空いたね」
ゲーム機を投げ出して進太が大声を出した。肘掛け椅子に座り、雑誌をめくっていたMの手が止まる。また進太が難題を持ち出しそうだった。
「Mのつくったご飯が食べたいな。家に帰っても、きっと食べさせてもらえないよ」
再び泣き出しそうな、情けない声で進太がMにせがむ。今日の朝食兼昼食は、出社の途中で外食することに決めてあった。元々料理などは得意でない。できるならば食べずに済ます方法を知りたいくらいだった。
「Mのつくったものは、みんなおいしいんだ」
進太が追い打ちを掛けるように言って、Mの顔を見上げた。
「素っ裸で料理はつくれないわ」
服を着るチャンスだと思ってMが即座に応える。
「ママは裸で料理もするよ」
にべもない答えがMを打ちのめす。家に帰っても昼食が食べられそうにない進太を、このまま帰すのが不憫になる。やはりMは負け続けるしかなかった。
「スパゲッティ・ミートソースをつくろうか」
「うん」
即座に進太の明るい声が部屋に響き、昼食のメニューが決まってしまった。
湯で上げたスパゲッティにレトルト・パックのミートソースをかけただけの食事を、Mと進太はテーブルに向かい合って食べた。
「M、おいしいね。Mのつくったものはみんなおいしい」
進太が歯の浮くようなほめ言葉を言う。だが、本当においしそうにスパゲッティを口に運ぶ。Mは料理の天才になったような気がしてまんざらでもない。本屋でレシピを買ってきて、真面目に料理を勉強しようと決心する。
「本当においしい。コンビニエンス・ストアのスパゲッティと同じ味だよ」
進太の一言がMの決心を粉々に打ち砕く。しょせん子供は正直なのだ。素っ裸で食べるレトルト食品の味が気分を最悪にする。黙って服を着ようとMは思った。もう一時間近く素っ裸のままでいるのだ。いい加減にうんざりする。
Mは黙って立ち上がった。
「悪いけど、家まで送ってくれない」
山盛りのスパゲッティを軽く平らげた進太が目を伏せたまま頼んだ。
「いつも一人で帰るでしょう」
答えたMの声がつい荒くなる。
進太は黙ったまま顔を伏せている。しばらくして小さな声で話しだした。
「僕はおいしいスパゲッティを食べたけど、ママはきっと何も食べていないよ。きっと叱られる。お願い。送っていって」
見下ろしたMの目に、半ズボンの裾から伸びた細い腿が見える。白い肌の上に幾筋もの赤い痣が盛り上がっている。部屋に来たときから気付いていた折檻の痕だ。自然に目頭が熱くなってしまう。
「送っていくわ。でも着替えるまで待って。午後は会社で仕事があるの」
Mが無理に明るい声で答えると、進太が顔を上げた。表情に輝きが戻っていたが暗い目をしている。不吉な予感がMにまで伝わってきた。 |