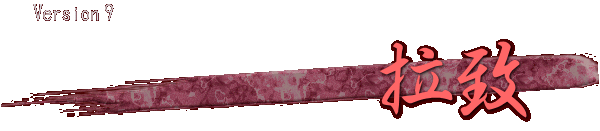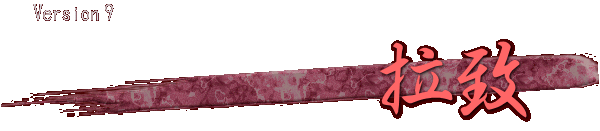未明から鳴り響き、降りしきった雷雨がようやく八時を過ぎて上がった。雲を割って一条の光が射すと、山地の谷間を覆っていた乳白色の霧が瞬く間に消滅していく。間近に迫った山塊に密集した、杉の梢越しに流れ去る霧が美しい。肌寒かった風に温気が混ざった。浅間山に通じる木橋の前で歩みを止めて、歯科医は天を仰ぐ。
「また暑くなりそうだ」
つぶやいた声が、意外に大きく耳に響いた。歯科医の頬が赤く染まる。耳が遠くなったことを過度に意識しているため、不意に耳を突いた自分の声が気恥ずかしかったのだ。もうじき歯科医は75歳になる。耳が遠くなり、目がかすみ、身体の動きが鈍くなっても文句の言えない歳だ。若い者たちとの暮らしがおっくうになることもある。中学生の進太はもちろんのこと、Mと比べても23歳も歳が違うのだ。もう祖父の役割さえできなくなるのかもしれない。そう思った瞬間、目元が潤んだ。かっと照りつける日射しが目の前に広がり、視界が真っ白になる。頭の芯が鋭く痛んで、両足がよろけた。真っ白だった視界が赤く染まり、大きく湾曲していく。急速に落下していく感覚に抗って両手を前に突き出した途端、夏草の上に大きく尻餅を付いた。白い麻のスラックスに雨水が染み込み、冷たい感触が瞬時に尻を覆った。
「情けない姿だ」
吐き出すように言って左右を見回す。見ている者があるはずもないのに、つい辺りをうかがってしまう自分が疎ましい。右手に握った紙袋からこぼれ落ちた河童人形が一体、夏草の茂みの上で歯科医を笑っている。手の上に乗ってしまうほど小さい、素焼きの粘土に彩色したクレードールだ。河童は小さく口を開け、心持ち尻を上げて寝そべっている。濃緑の夏草の上に載ったもえぎ色の妖怪は、本当に嘲笑っているように見えた。どことなく進太の笑いに似ている。
「作者を笑うとは失礼千万な奴だ」
まんざらでもない声で言って手を伸ばし、クレードールを掴んで目の前にかざし、鋭い目でみる。思いの外できが良いのに驚き、素焼きのまま河童神社に奉納するのがもったいなくなる。河童神社は浅間山の山頂にある神社の仮称だ。もっとも、山と言っても標高八十メートルほどの小山で、神社も祠と呼んだ方が当たっていた。若いころの歯科医が酔狂で購入した裏山にあった見捨てられた祠を、何を祭っていたのか分からないまま河童神社にしたに過ぎない。すべては歯科医の趣味の陶芸から始まる。
「最初の河童祭りは楽しかったな」
小さくつぶやいて、歯科医は手に待った河童から目を離した。木橋からは見えない山頂の方を見上げて、大きな溜息を付く。左手を濡れた地面に当て、両足に力を入れて立ち上がった。びっしょり濡れた尻が気持ち悪かったが、十体の河童人形が入った紙袋をぶら下げて木橋を渡り、山頂の河童神社に続く山道を踏み締めた。河童の人形を山頂の祠に奉納し、見晴らしの良い場所で飲食を楽しむ河童祭りは、4年と続かなかった。一家の習俗と呼ぶには、はかなすぎた。
最初の祭りは6年前の秋に遡る。歯科医とMと進太の3人で暮らし初めて、半年が過ぎたころのことだ。その年の4月に教護院を措置免除になった進太をMが引き取り、歯科医院の敷地に建つ蔵屋敷で二人で暮らしだした。Mは自殺した一人息子のピアニストの妻だ。そのMが養子にした進太は、戸籍上の孫になった。歯科医は今も蔵屋敷から少し離れた母屋で暮らしている。いくら義父とはいっても、かつて官能を共にしたMと一緒に暮らすのは気恥ずかしかった。Mもあえて蔵屋敷で同居しようとは言わなかった。3人一緒に過ごす時間は食事と、それに続く団欒に限られていた。だが、山地に来たころの進太は、妙におどおどとした態度が目立った。6か月続いた教護院の暮らしがどんなものか、歯科医には想像もつかなかったが、幼い進太の心に深刻な影響を与えていることは確かだった。食事の途中で怯えたように歯科医とMをうかがう目は、特に胸に応えた。気に添わぬ食事を、無理して食べる姿が不憫を誘った。勝手気ままにMに甘えていたという話が、まるで嘘のようだった。刑務所の生活を体験しているMは、そんな進太に過剰に反応した。進太と暮らして2週間も経たないうちに、食事は進太の気に入るものだけを選んでいた。また、進太の気に染まぬことは、すべて遠ざけるようになった。小学校二年生になっていた進太は山地の学校に馴染まず、一学期のほとんどを休んだ。歯科医の目には、Mの過保護と過干渉だけが目立った。話に聞いた、実母の睦月の行動と大差がないようにさえ思えた。見かねた歯科医は学校が夏休みになって以降、一日の大半を蔵屋敷で過ごすことにした。趣味のアトリエをまた再開したのだ。今度は一心に粘土をこね、様々な格好の河童を3人で一緒に作った。何で河童だったのか今は定かでない。皿や茶碗など散々試みたあげくに犬や猫などの動物を作り、最後に進太が興味を示したものが河童のクレードールだった。歯科医が作る河童は、取り分けひょうきんに見えた。目を輝かせて粘土細工を手伝う進太を見ていたMの、うれしそうな視線が忘れられない。
歯科医は山地に伝わる河童伝説を創作し、川で泳ぐ子供や釣り人が水底に引きずり込まれないように、河童祭りをすることを提案した。恐ろしい妖怪である河童に、愛らしい人形を供えることで凶暴な怒りを静めることができる。河童を祭った神社は、裏山の頂にあるんだと言ったのだ。
「ぜひお祭りをしようよ。歯医者さんの楽しい人形で神社を一杯にしよう。だって、僕は川で泳ぐのが好きなんだ。河童に意地悪はされたくない」
喜々とした進太の声が耳を打った。きらきらと輝く目が忘れられない。
「ねえ、M。祭りの日はごちそうをつくってよ。河童神社の前で3人で食べよう。きっと河童も喜び、川で悪さをしなくなるよ」
続けて言った進太の言葉に、目を潤ませてうなずくMの顔が、目に浮かんだ。あの時やっと、再び進太が心を開いたのだ。ごく普通の楽しい家庭生活が始まる予感が、歯科医の全身を満たしていた。
息を切らせた歯科医の目の前に、貧相な祠があった。夏草に覆われた石の祠の前に、小さな河童人形が山になって苔むしている。赤や青、黄で彩色した色は雨露で流れ、赤黒い素焼きの地肌が累々と露出している。歯科医とMと進太の3人で弁当を広げ、酒を飲んではしゃいだ最後の河童祭りから、もう4年が過ぎた。その後も毎年、未練の妄執に駆られるように訪れるのは、歯科医だけだ。若い者たちは、毎日の暮らしの忙しさに流されていった。小さな祝祭が続くはずもない。家族の気持ちも変わっていくのだ。年老いた者だけが、取り残される悲哀を感じる。だが、過ぎ去った思いは戻りはしない。空しく時が流れ去り、人は老いていくだけだった。2年前の70歳の誕生日を契機に、歯科医は一切の診療をやめた。新しい家族が3人そろった食事も、今年からしなくなった。中学校二年生になった進太は、自分の部屋で食事をとる。Mも疲れている。色々なことがあった。歯科医の最後の趣味になるクレードール造りだけが、高度になった技術に裏付けられて、今も続いていた。真っ青な夏空が小高い山の頂に広がり、遠くカナカナゼミの声が聞こえてくる。立ちつくす歯科医の頬を、涼しい風が撫でていった。今年の夏がまさに、去ろうとしているかのようだ。
ズガーン、ズガーン、ズガーン
周囲の山々にこだます鈍い銃声が、祠の後ろで轟いた。かん高いエンジン音が、銃声に被さる。晩夏の山地の静寂を、一瞬に音の暴力が引き裂く。足に絡みつく夏草を分けて、歯科医は祠の裏側に回った。西に開けた視界の先一キロほどの所はもう、峻険な山が迫っている。そのまま見下ろしていくと、小高くなった山懐に日射しを浴びて輝くドーム館が見える。山を背にしたドーム館の長大な駐車場が壊され、今はクレー射撃場に代わっている。弾避けのために山肌が醜く削られ、露出した赤い岩盤が陰惨な印象を伝える。射撃場が完成したのは、つい一か月前だ。昨年の夏の終わりに、アメリカから帰ってきたチハルが造成したものだ。見下ろす歯科医の眉が曇る。また銃声が響いた。猟銃を構えたチハルの姿が眼下に小さく見える。また硝煙が上がり、バイクのエンジン音が轟いた。山裾の道にグリーンのバイクが現れる。凄いスピードでドーム館を目指して上がっていく。ヘルメットも被らずに50ccのモトクロッサーを飛ばすのは、進太に違いなかった。夏休みに入ってから毎日、進太はバイクでチハルの元に通っている。きっと銃を撃たせてもらっているに違いないと、歯科医は思う。いくら交通量の少ない山地だからといって、ナンバーが交付されないモトクロス用のバイクを、免許も持たない進太に買ってやったMの気が知れない。とにかく、チハルが帰ってきてからろくなことがない。あの無惨な殺人事件が起こったのは確か、チハルがドーム館に帰り着いてすぐのことだったと思う。まさか、小学校の六年生が、こんな平和な山地で殺されるなんて、それもMが相続したこの裏山の裾で死体が発見されたのだ。
歯科医は嫌なものでも見たように、目をしょぼつかせてからドーム館に背を向けて祠に戻った。そのまま山頂の南端までいって、開けた谷を見下ろす。市へと下る山根川の対岸に小さな学校が見える。それぞれ一学級ずつしかない、小学校と中学校が合い向かいに同じ敷地に建っていた。校庭と体育館、プールは供用だが、どちらの校舎もまだ新しい鉄筋コンクリート造りの二階建てだ。裏山と向き合っている校舎が中学校だが、今は夏休みで人影もない。だが、休みが終わったからといって、進太が通学するかどうかは不明だった。また嫌なことを思い出してしまったと後悔して、歯科医は東側に回る。東は急斜面になって沢に落ち込んでいる。鋭い角度で見下ろした沢の手前の狭い山裾にワサビ田が見える。ワサビ田の下は農道で、その先は浅間山から続く小高い瘤山が迫っている。わずかに水面を輝かせている五枚のワサビ田は、ほとんどが日の当たらない山陰に位置していた。清流の流れる沢の向かいは歯科医院の敷地だ。蔵屋敷の裏の梅林が見える。だが、蔵屋敷に渡るには不安定な丸太橋を歩くしかない。ワサビ田の隅に人影が見えた。作業服姿の長身が俊敏に動き、長い髪が揺れた。Mがワサビ田の雑草や枯れた葉を取り去っているようだ。熱心に動き回るMを、歯科医は不思議そうに見下ろす。たとえ山地に住んだからと言って、Mが百姓仕事に精を出すとは、今でも信じられない。Mがワサビ田を開いてからもう、五年になるのだ。
小さく首を振りながら歯科医は祠の前に戻った。どれほど長く生きたとて、ろくなことはないと思い、祠の前にしゃがみ込んで紙袋から河童人形を取り出す。窯焼きにまわすのを思いとどまった歩留まりの品だが、その一つ一つが今日は妙に懐かしい。十体を石の上に並び終えてから、クリスタルのデカンターに入れたワインを紙袋から出した。ブルゴーニュの赤を一口含み、不味そうに飲む。真ん中に置いた寝そべったクレードールの顔にも一滴垂らした。笑っていた顔がワインを浴びて泣き出しそうになる。不意に河童の顔がピアニストの泣き顔に変わった。十八歳の時の純真な泣き顔だ。歯科医は激しく頭を左右に振った。また嫌なものを見たと思った。やはり長く生きすぎたのかもしれないと、乾いた悲しさが目の底を掠めた。 |