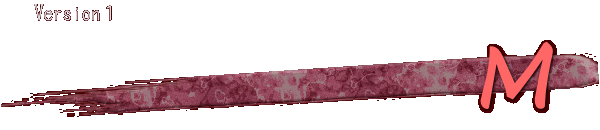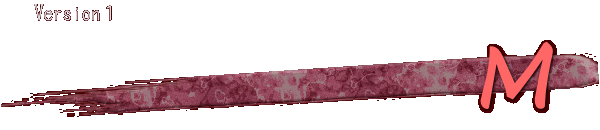「夢のような話をしようか」
振り返った彼は私の目を覗き込むようにして、よく通る美しいバリトンで言ったのだ。
今日初めて聞く誇らしい声音に驚き、反射的に聞き返そうとしたが、彼はすぐ背中を見せ二、三歩踊るように歩いて、そのまま日本海へと張り出した断崖から海へ墜ちて行った。
残された私に向かって、海から吹き上がって来る風があまりに強かったので、ひょっとすると彼は、鳥のように再び舞い上がって来るかもしれないと思ったのだが、いつまで待っていても冷たく強い季節風に私は、煽られるばかりだった。
私の思いが甘かっただけだ。彼が鳥になるなんて、とてもできない相談だった。 だって彼は、生まれたときと同じ素っ裸で後ろ手に縛られ、肛門には黒い皮鞭の柄を深々と突っ込まれていたんだ。そんな姿の彼が、鳥のように舞い上がって来るなんて事は、とても許されるものではなかった。
しかし、と私は思う。
取り残された私はいったいどこへ行けばよいのか。なんのために彼の希望を入れて、こんな地の果てのような場所に来たのか。なぜ、初冬の日本海が見える断崖で震えていなければならないのか。
私は無性に腹が立った。
おまけに右手はまだ、彼の肛門へと続いていた鞭の先を、しっかりと握っていたのだから呆れる。
私は寒さに震え眉を寄せながら、彼の遺品となったに違いない黒い皮鞭を手元にたぐり寄せた。鞭の柄に思わず鼻先を寄せると、彼のきつい排泄物の臭いがする。急に懐かしさがこみ上げ、頬に涙が流れた。
両手で彼の体温を感じ取ろうと撫でさすってみたが虚しく、冷え冷えとした皮革の感触だけが両のてのひらに残った。
この鞭は、彼が凄い速度で断崖から海へ墜ちて行くとき、私と彼とを真っ直ぐに繋いでいたのだ。この右手は鞭の柄が彼の肛門から抜ける瞬間、ぴんっと張った鞭先を通して、彼の全体重を一心に支えたはずだったのだ。
しかし今、右手は何の感覚も残していない。
私は大切なものを取り逃がしてしまったような気がして、鞭を握った右手を嫌々をするように激しく振った。手元を離れた鞭は闇に紛れるように飛び去り、彼同様、断崖の上から暗い海へと落ちて行った。
もう私には何も残ってはいない。
やはり彼は逝ってしまったのだと、いまさらながらに思い知ったが、もはや頬を流れる涙もなく、ただただ冷たく強い季節風を全身に感じるだけで、私は逃げるようにヒーターの効いた車へと急いだ。 |