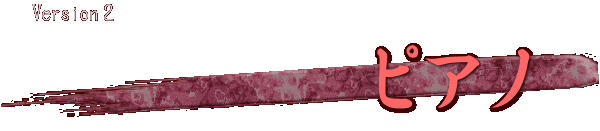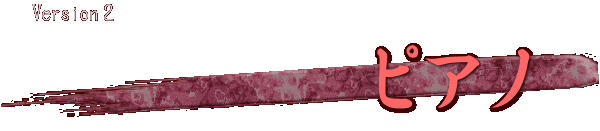背後でドアが開いたことは分かっていた。
ピアノのペダルを踏む足元に冷たい空気が流れて来たし、静かにそっと近付いて来る人の気配も感じていた。しかし、僕が練習している「スケルツォ第二番変ロ短調」はエンディングに差し掛かっていたのだ。後ろを振り返っている余裕などはなかった。
思い切ってFを打鍵しようとした瞬間、耳元にふっと吹き掛かる息を感じた。暖房のきいたスタジオだったが、熱く感じられた息に戸惑い、僕はめちゃくちゃに音を外してしまった。
かっと顔中に熱が回り、真っ赤になった僕は、残ったフレーズをもの凄い速さで弾ききってしまった。
「素敵なショパンをありがとう」
拍手とともに耳元で、きれいなアルトが響いた。
どぎまぎして振り返ると、驚くほど近くに目鼻立ちのくっきりした女性の顔が見えた。
彼女は暖かそうな微笑みを浮かべ、手を差し伸べて来た。
「ミスっちゃって、すみません」自動的に言葉を繰り出し、差し出された手を握り返した。気分はもう完璧にピアニストだった。ミスタッチはあったが、とにかく今日の演奏は気に入っていた。演奏を認められたことで、胸の鼓動がおかしいほど高く鳴り響き、それを彼女に聞かれてしまうことだけを気にした。
トラッドなスーツに身を固めた彼女はとてもシックで、大人の女の雰囲気を嫌になるほど見せ付けていたのだ。
「君の音楽をもっと聴かせてもらいたいのだけれど、先生にも会いたいと思っているの」
「先生は今日、もう戻っては来ません」
「そう、困ったなー。君は先生の生徒なのかな。ミニコミ紙に載せるコマーシャルのことなんか、聞いてはいないよね」
「知りません。編集の方なんですか」
「編集はこういうことはしないの。私は営業で来たの。君にとっては皆同じようなものかも知れないけれど、業界の中ではずいぶん違うんだよ」
なれなれしい言葉遣いだったが、不思議に嫌悪感はなかった。
「まっ、また顔を見せるから、先生によろしく言っといてよ」
ぞんざいに言ってから少しの間沈黙し、自分の存在を強く印象付けた後、おもむろに言葉を続けた。
「もし差し支えなかったら、音を外さないスケルツォを聞かせてくれない」
彼女の一言で、あれほど気に入っていた演奏が急にみすぼらしく思え、無様な音を聞かせたまま帰すわけには行かないと思った。むろん渡りに船の心境だ。
僕は大きく深呼吸してから、スケルツォを曲芸のように弾き始めた。不思議と音も外さず、僕自身のリズムも守ったまま、曲はエンディングへとなだれ込む。
最後のDesを、すっと全身で、気分良く置いた途端。
「ヴラヴィッシモ」と声が掛かった。
冬のさなかに全身から汗を流し、顔を真っ赤にさせた僕の頬に、彼女の唇が触れた。頬に幾つもキスされた後、逃げるようにして避けた唇に、彼女の唇が重ねられた。鼻先に突き出された唇のルージュは、多分ゲランだった。恐らく、熱くなった彼女の身体から漂う香りもまたゲランだった。
僕は、唇に合わせられた柔らかな感触を艶めかしく感じながら、母と同じゲランの香りを二度嗅いでいた。ペニスが熱く、むらむらと勃起してきていた。
「うっー」
突然低い声を上げた彼女が、床に屈み込んでしまった。オーバーな身振りにあっけにとられ、気が動転してしまった僕も、いつまでも起きあがらない彼女が心配になって屈み込んだ。腰が下りきる瞬間、彼女の手が股間に伸び、勃起したペニスをつかんだ。
「何をするんですか」と声を荒立てると、
「歯が痛いのよ」と、のんきそうなアルトで甘える。
「そんなに歯が痛いのなら、歯医者に行かなければだめですよ」と勧めると、「君はピアニストだと思っていたが、歯医者の回し者なのか」と毒づく。
見ず知らずの、初対面の女に絡まれては、かなわないなと思っては見たが、これも行き掛かりのサービスだと考え直し、我が家の営業活動を開始した。
「僕の父は歯医者なんです。良かったらうちで診察を受けませんか」
「へー、ピアニストの父はデンティストなんだ」と、はすっぱな言い方でいたずらっぽく僕の目を見る。
目が合った途端、再び痛そうに顔をしかめた彼女は、
「事のついでに案内してもらおうかな。でも私は、保険証は持っていないよ」と言ったのだ。
悪い客を捕まえてしまったと後悔したが、結構父といい勝負になるかなと考え直し、案内することにした。
「でも、このスタジオを開けっぱなしにしておいていいの」
似つかわしくない常識的なことを言う彼女に、僕は心の中で笑ってしまった。
「別に、留守の間に泥棒が入っても、あなたの広告料がパーになるくらいの損害しかないんじゃあないですか」
「君はなかなか賢いね。ピアニストにはもったいないくらいだ。それに、大人をからかうのも得意みたいね」
「別にからかってるわけじゃあないけれど、あなたは普通の大人とはちょっと違うみたいだ」
「多分、私は君の将来のために、大人のあり方をよく説明した方がいいのかも知れないけれど、歯が痛くて仕方がないから、とにかく、君の推薦する名医のところに早く案内してちょうだい」
彼女は話し掛けながら立ち上がり、片手に持っていたシェラデザインのマウンテンパーカーに袖を通し、外に出て行こうとする。
随分せっかちな女だと、あきれ返って後に続くと「お揃いのパーカーだね」と前を見たまま言った。
確かに、彼女はタンで僕はグリーン。色違いの揃いのパーカーだった。
玄関を開けると真ん前に図々しく、真っ赤なユーノス・ロードスターが駐車してあった。しかも、この寒いのにオープンにしてある。道理でマウンテンパーカーを着込んだわけだ。彼女を案内するのは、並の仕事では済みそうにない予感がした。うれしい予感につい、口元が緩んでしまう。
「何をにやにやしているのよ。早く乗りなさいよ」
僕が乗り込むとすぐ、凄い速度で急発進する。行き先も聞かなければ方向も確かめはしない。
メインストリートの車の流れに、強引に割り込んでから「どっちに行くの」と、子供みたいに聞いた。
「山地に行ってください」と答えると、急に車のスピードが落ちた。
一瞬の重い沈黙の後、スピードが上がり、対向車が途切れた瞬間を突いて鋭くUターンした。
「反対方向ですみません。でも、凄い運転ですね」
「ピアニストの家は山地なのか」
彼女は独り言のようにつぶやいたきり黙り込み、よく知った道をドライブするようにスムーズに運転する。交通量が少ないのに、遅すぎるとさえ思われるほどにしっかりと、制限速度を守って走る運転が不思議だった。
山地という言葉が引き起こした不自然な沈黙に驚き「意外に安全運転なんですね」と、気を引くように尋ねると、
「捕まれば懲役三年だからね」と、わけの分からぬ返事が返ってきた。
せいぜい罰金と免許停止ぐらいな事は僕も知っていたが、聞き返すことがためらわれてしまった。
「君は、山地の古い家を知っているかな」
突然彼女が聞いた。多分あの、主人が自殺したことで騒がれた築三百年の家のことだろうと思ったが、
「知りません。僕の家はそんなに山奥ではないんです。あなたの言っている家は多分、昔林業で栄えた山林地主の家だと思うけど、僕の家は代々材木商をしていたんです。だからずっと手前にある」と答えてしまった。
「そうか、ピアニストの家も資産家なんだ。商売を嫌ったおやじさんが、歯医者になったってわけ」
「いいえ、父は婿なんですよ。資産家なのは母の方で、父は半ば趣味で歯医者をやっている」
再び会話が弾むようになったが、僕は身元調査をされているような不快感を感じた。しかし、積極的に家庭内のことを話しているのは僕なのだからあきれる。「ミニコミ紙の営業は長いのですか」と話題を変えると「昨日からやってる」とにべもない返事だ。
「私は二十七歳だけど、ピアニストは幾つ」
「十八」
「へー、高校三年生か。ずいぶん余裕があるね、歯医者の受験勉強はしなくていいの」
「あなたは営業だけでなく、説教もするんですか」
「ごめん。怒らせてしまったかな。確かに、私の知っている君はピアニストであって、受験生ではないものね。余計なことを言ってごめんなさい」
急にしおらしいアルトが口を突き、僕をどぎまぎさせる。追い打ちを掛けるように「君のペニスは大きいんだね」と続けた。
寒い風にあおられる頬が真っ赤になってしまい、先ほどペニスをつかまれた感触が甦り、またむっと勃起し始めていた。
「勃起してくれたんだね」
「下ろしてください。もう嫌ですよ」
「怒らなくてもいいでしょう。事実なんだから。私は嬉しく思っているのだから、恥ずかしがる必要なんてないじゃないの」
「でも、初対面で交わす会話だとは思えませんよ」
「君はペニスみたいに、かちかちに固いんだね。私だって大人なんだから、人を見て話をするわ。君は見くびられたと思うわけ」
「いいえ」
「私は女として、男の君に話し掛けているのよ。それとも、女と性の話をするのは嫌いなのかな」
とんでもないことになったと僕は思った。もちろんピアノと同様、性にも強い関心はあるし、毎晩のようにマスターベーションもしている。しかし、大人の女から露骨に性の話をされても困る。まるで誘惑されているようじゃないか。
「私は、ピアニストを誘っているのよ」
運転しながら僕の方を向いて、ゆったりとしたアルトを響かせた彼女の目をじっと見つめた。
絡み合った二人の視線がスパークし、股間で膨れ上がっていたペニスが暴発した。暖かい液体が腿の付け根に広がっていく感触が、とにかく不快だった。
そんな状態に気が付いたのか、付かないのか。ちょうど差し掛かった渓谷沿いのカーブで、彼女は視線を前方に戻し、大胆にハンドルを切った。
僕は射精したことを気付かれてもいいと思った。きっと、彼女も喜んでくれるはずだと思ったのだ。ほんのちょっとの時間しか経っていないのに、僕は大した変わりようだった。ピアノも性も、個人教授でなければ上達しない。
僕は晴れやかな気分になって、オープンの車内に吹き込む寒い風に向かって、わっと大きな声を上げた。
隣で運転する彼女が、くすっと笑ったような気がした。 |