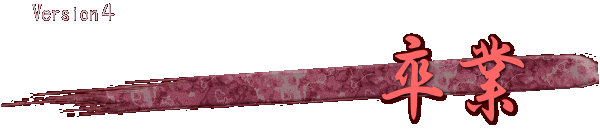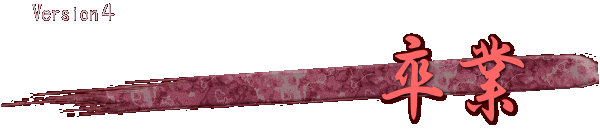市は、三方を山が塞いでいた。
開かれた南には関東平野が広がっていたが、その入り口を握するように水瀬川が滔々と流れている。上流にある、かつて鉱山で栄えた町の山脈に源流を発する大河だった。
辛うじて北に延びた谷だけが、水瀬川に注ぎ込む渓流沿いに延々と三十キロメートルほど続き、山脈に突き当たって絶えていた。
一言でいって谷間の街だ。都会までは、鉄道で一時間二十分。自動車で行けば、高速道路を使っても約二時間の距離だった。
決して交通の便の良いところではない。水瀬川を遡航する船便が絶えてからは、他市に秀でた交通網は持たない。その水運が栄えたのも、百年以上も前の話だ。
農地の少ないこの地方は、水運による鉱石の出荷と、この市で製造する絹織物の販売で栄えてきた。
特に、千二百年の伝統を豪語する絹織物は、幕末から明治期にかけて工場制手工業として飛躍的に発展した。
機を織るのは、主に女性だった。その織姫と呼ばれた女工たちを管理するのもまた、女性だった。男たちは、独特の文化と呼ばれるようになる趣味道楽に、湯水のように金を使うばかりだった。
生産実務者としての女性は、多忙を極めることになる。機業の管理運営に関する教育が求められたのも、当然の話だった。幕末期から私塾で学ぶ女性が多く、官制の学校も女学校が一番先に設置された。
女性の献身的な労働と、学識が街の発展を支えて来たといっても過言ではない。この女性教育の一翼を担い、機業家の婦女子に読み書きや算盤を教えた私塾を基盤に、昭和初期に設立されたのが命門学院だった。
現在の命門学院は、幼稚園から大学まで網羅した、地方教育界の雄として名声を誇っていた。女子大学部は水瀬川を越えた広々とした平地に移転して久しかったが、男女共学の高等部まではまだ、この谷間の街の山際に点在していた。特に中等部と高等部は、都会の名門大学に数多くの合格者を出す進学校として名が高かった。建学の精神とは離れ、受験戦争を勝ち抜いていくことを目的にした学校経営だったが、厳選した生徒の質を誇っていた。
鉱山の町の廃校となる分校で小学校を卒業し、中学進学を機に両親と共に市に転入してきた祐子は、命門学院中等部の三年生になっていた。この市での生活も、もう三年目になる。
祐子は、水道山の麓にある中等部の裏門から校外に出た。
真っ直ぐ、山を越えるアスファルト道路を歩いて行く。いつもは正門を利用し、街の北にある自宅のマンションに向かう。裏門から山に続くこの道は、なだらかな山頂にある配水場の横を通り、街の西側へと続いていた。ちょうど、街を半周してから自宅に帰ることになる。長い道のりだった。
どんよりと曇った六月の空から、いましも雨が落ちてくるような気がする。
祐子は、うんざりした顔で立ち止まり、白い長袖のセーラーの胸元を飾る赤いスカーフを、心持ち緩めた。梅雨寒の冷気が豊かな乳房に触れた気がして、細い肩をすくめる。
身長百六十センチメートルの背を少し屈み気味にして、また歩き始めた。
祐子は、背が高いことと、彫りの深い大人びた顔が、目立ちすぎて嫌いだった。特に、同じ制服を着た少女たちの中では周囲の注目を集めた。早く制服のない高等部に進学したかったが、まだ一年近く先のことだ。祐子には一日でさえ、十分長く感じられる。
急な坂を越えると、なだらかな道の先に美術館が見えてくる。確か、性と死を描いた作品だけを集めた企画展が始まっているはずだった。人目を引くようなポスターが張り出されているわけでもないのに、むず痒い不潔感が喉元にこみ上げてくる。そっと息を吐くと、言い知れぬもどかしさで全身が震えた。時の流れが遅すぎるのだと思う。
鬱屈した気持ちに任せ、路上の小石を力いっぱい蹴った。乾いた音を立てて転がっていった小石は、美術館の前で止まった。
駐車場から凄い速度で出て来た赤い車が、その小石をタイヤで跳ね上げる。低いエンジン音が、山裾の雑木林に響き渡った。
直進して来た車が急ブレーキをかけ、祐子の横に運転席が並んだ。
「祐子じゃない。久しぶりね」
オープンにした真っ赤なMG・Fから、明るく女性の声が響いた。心持ち小首を傾げた懐かしい笑顔を運転席に認め、即座に祐子の表情が輝く。
「Mはいつも素敵ね。車を替えたの」
「三年生になったらお世辞が上手くなったわね。この車は借り物よ」
アイボリーのスーツ姿のMが、長い髪を風に揺らせながら楽しそうに応えた。
「どこへ行くの。家と反対じゃない。美術館に来たの」
「山の下の老人ホームに行くんです」
「そう、送っていくわ」
Mは一瞬美しい眉を寄せ、怪訝そうな顔をした。そのままMG・Fをスタートさせ、五メートル先で見事なスピンターンを決めて戻って来る。
「さあ、乗りなさい」
祐子が乗り込むと直ぐ、車はスタートした。しかし、いつものMに似ず、急な加速をしない。路上に張り出した緑濃い枝の下を、ゆっくりと坂を登って行く。
「老人ホームに何の用があるの」
少し走ってからMが訊いた。
「鉱山の町の弦楽五重奏団を覚えてますか」
「もちろん覚えているわ。あなた達と裸になって御神輿を担いだとき、モーツァルトを演奏してくれたよね。あの時の痩せっぽちの裸んぼが、こんなに魅力的な女になっちゃうんだから、私も年寄りの仲間入りかな」
祐子の頬が赤く染まった。
「あの時の第一ヴァイオリンのお婆さんが、老人ホームで病気になったんです。町役場の村木さんが手紙で父に知らせてくれたんだけど、父はこのところずっと都会暮らしで帰ってこられないの。週末は母も父の所に行くから、私が代わりにお見舞いに行くんです。Mの所へは連絡がなかったのね」
「そう。中央官僚のお父さんを持つと大変だね。私はしばらく家に帰ってないから、手紙が来ても読めないのよね」
祐子は首を曲げて、Mの横顔をまじまじと見てしまった。
「あんまり見つめないで。私はいつもと同じよ」
確かにMの言う通りだと祐子は思った。Mは、自分の暮らし方はいつも自分で決めるのだ。羨ましさが、胸をよぎった。
「Mは変わらないのね」
「どうしたの、しんみりした声を出して。私だって変わっていくわ。きっと祐子の時間が目まぐるしく過ぎて行くから、私の変化に気付かないだけよ。その証拠に、祐子は凄く美しくなったよ。これからもどんどん変わっていった方がいい。姿だけでなく、考え方や、感じ方も。止まってしまうと、その若さで腐ってしまうよ」
「ええ、私は変わっていくみたい。みんな遠くなっていってしまう」
「寂しそうな声を出さないの。懐かしく思いさえすればいいことよ。修太はどうしているだろうね」
「知らないわ」
「同じ中等部の光男には、毎日会うでしょう」
「顔を見掛けるだけだわ」
「そう。話に乗ってこないのね。三年前の夏、六年生の裸んぼの時、光男は祐子のことを好きだったのよ。少女になり掛けの裸を、眩しそうに見ていたわ。知ってた」
「知っていたわ。でも、あのころの話はしたくないの。話されるのも嫌。もう、ずっと遠い昔のことのような気がする」
「あなたが何に反発するのか知らないけど、過去のことを悔やむのはとても悲しいことよ。今の祐子は、あの時よりずっと美しくなっているのだから、それを用意してくれた過去も好きになれるといいね」
「私は美しくなんかない」
突然の大声が、Mの耳を打った。
変わらないのは祐子の方だとMは思う。知識や意識、認識する能力など、自分自身をコントロールする力が、身体の成長に追いついていけない不器用な少女が助けを呼んだのだ。急に、まだ少女になり掛けだった、小学校六年生の祐子を懐かしく思い出した。瑞々しい裸身に、萌えだしたばかりの陰毛がとてもいじらしかった。あの時と比べ、ほとんど変わっていないとさえ思えてしまう。胸の奥がキュッと熱くなった。まるで、祐子の保護者になった気分だ。
Mは大声を無視して、祐子のスカートの下に左手を素早く伸ばした。ほんのりと湿り気を持った若い肌が、手のひらにぴったりと張り付いてくる。
「アッ」と小さく上げた声にお構いなく、手を股間へと伸ばす。祐子の両腿が固く合わせられる。強引にショーツの下に潜り込ませた指先に、髭の剃り跡を撫でる感触が伝わる。反射的に横を向き、祐子の横顔を見つめた。真っ赤に染まった頬が微かに震えている。
MG・Fのノーズが左右に振れた。思い切ってブレーキを踏む。アンチロックブレーキの制動力が四輪をコントロールし、車は路肩に沿って危なげなく止まった。
ぽつぽつと降り始めた雨が、上気した二人の頬に落ちた。
「祐子、ショーツを脱ぎなさい」
股間に手を入れたままMが命じた。
「いや。恥ずかしい」
消え入りそうな声で、うつむいたまま祐子が言った。
「何も恥ずかしいものなど無いわ」
鋭く言ってMは、右手で自分のアイボリーのスカートを乱暴にまくり上げた。腰をずらして、股間を剥き出しにしたままスカートを止めた。いつものようにショーツは穿いていない。両足を広げ、黒々とした陰毛を細かい雨に打たせた。熱くなった性器に冷たい雨滴が当たった。
「さあ、祐子も脱ぎなさい」
促された祐子が腰を上げて、渋々ショーツを下ろした。
陰毛を剃り上げられた股間に小さな水玉が幾つもできていく。可愛らしい割れ目から、小さな性器がピンク色の顔を覗かせていた。
「自分で剃ったの」
「そうよ」
「どうして」
訊いてみてからMは、問いの虚しさに思い当たった。
「三年前の夏。鉱山の町に来たMと同じようになりたかったのよ。勇気が湧くから。Mが楽にして上げたカンナのことを忘れたくないから。私が殺した産廃屋のことも忘れたくないから」
あの夏の出来事が、凄まじい速さでMの脳裏を駆け巡った。カンナに剃り落とされた頭髪と陰毛の感触が、一番はっきりとした記憶となって甦る。その、つるつるの股間を吸って窒息死したカンナの安らかな死に顔が、悲しく思い出された。
祐子はまだ、あの時の影を引きずったまま生きていたのだ。祐子への愛おしさが募る。
これまで、何回となく祐子と会っていたが、話らしい話をしてこなかったことが悔やまれてならなかった。
「友達はいるの」
また陳腐なことを訊いたと思ったが、祐子ははっきり首を横に振った。
「独りぼっちなんだね」
最悪の言葉に、自分自身腹を立て、祐子の股間に置いた手で無毛の陰部を優しく撫で回した。
「先輩がいるの」
ぽつりと祐子がつぶやいた。
「高校の先輩なの。だから、高校に進学してから先輩になるんだけど、今から先輩だって思ってるの」
訳の分からない言葉だったが、明るい声のトーンが救いになった。
祐子の言う先輩とは、ひょっとして男ではないかと思ったが、聞きただすことができなかった。
Mは、胸の底に沈んだ疑問を無視してアクセルを踏んだ。最後の急坂を一気に上り、MG・Fは水道山の頂まで登り詰めた。青々とした芝生の広がる配水場の入り口に、洋風建築を模して大正期に建てられたという水道記念館が、瀟洒な姿を見せている。
雨はやみそうもなかった。
「トップを掛けるわ」
記念館の前で車を止めたMは、祐子に声を掛け、座席の後ろに折り畳んだ黒い幌を引き上げた。広々と野外と通じ合っていた車内が、途端に狭苦しい空間に変わる。二人の女が体温と共にあげる温気がむんむんと匂い立った。
鬱陶しさに首を振って、Mはエアコンのスイッチを入れ、力強くアクセルを踏み込み、長い下り坂をスピードを上げて下った。
急坂を降りきったところで右に曲がると、老人ホームに通じる道に出る。鬱蒼とした木々の影に見え隠れする、病院のような白いコンクリートの建物を見ながら走ると、特別養護老人ホームと記した門柱が現れた。
随所に植栽した広場の先に、広い車寄せを張り出した玄関があった。
車窓越しに見る玄関は静まり返っている。ドアボーイが出払ってしまったリゾートホテルの玄関ホールのようだ。左側の車寄せにMG・Fを止めたMは、先ず黒い幌を畳んだ。
「息苦しかったわね。二人乗ると雨が恨めしくなるわ」
開放感に満ちたMの声を、けたたましいエンジン音がかき消す。
門柱の脇を車体を斜めにして回り込んだ大型のオートバイが、右側の車寄せで急ブレーキをかけて止まった。
カワサキの400CCに跨った男は、赤いフルフェースのヘルメットを被っていた。紺のジャンパーの襟元から、白いシャツと臙脂のネクタイが覗いている。オートバイと不釣り合いな服装だった。
Mは値踏みするように男の姿を見てからドアを開け、車を降りた。もの珍しそうに建物を観察しながら、玄関の自動ドアの前まで来る。
「面会ですか」
背後から明るい声が呼び掛けた。振り返ると、オートバイから降りた男がヘルメットで乱れた髪を手で掻き撫でながら近付いて来る。
「やあ後輩、俺も中等部から命門学院に行ったんだ」
馴れ馴れしく祐子に話し掛ける。
百八十センチメートルほどはある、しなやかな身体の上で、物怖じしない機敏そうな若い顔が笑っている。
「随分時代が変わったもんだ。俺が中等部にいたときは、後輩みたいに可愛い子は二人といなかったもんだよ」
「一人は、いたってこと」
顔を伏せてしまった祐子の代わりにMが、青年の熱く燃える目を見据えて応えた。
「失礼しました。あまりに制服が懐かしかったので、勝手に話し掛けてしまいました。ごめんなさい」
いたずらを見咎められた子供のように、顔を赤くした青年が深々と頭を下げた。
「私はこういうものです。よろしければホームをご案内します」
差し出された名刺から、青年は天田といい、この市の福祉事務所のケースワーカーだということが知れた。
「私は夕刊ポストの記者のM。ぜひ、案内してください。でも、その前に今の質問に答えてくださる」
Mが笑顔を見せて応えた。日刊の地方紙の嘱託でも記者には違いなかった。
「新聞記者だったんですか。弱ったなあ。でも俺が悪いのだから答えますよ。中等部にいたころ、妹さんそっくりの美人が一人だけいました」
「好きだったの」
「もちろんです」
祐子の姉にされてしまったことをくすぐったく感じながら、Mは久しぶりに愉快な会話を笑顔で楽しんだ。
都会での学生生活を四年間送り、就職で市に帰って来たというフレッシュマンに、Mは鉱山の町の第一ヴァイオリンの老女の名を告げた。
「あの身寄りのないお婆さんの知り合いなんですか。あの人は俺が担当しているんです。鉱山の町からの依頼で、このホームへの入所を決めました。初仕事だったんですよ。それが、病状が思わしくないというので、休日に呼び出されました。ご一緒しましょう」
天田は先に立って、勝手知ったホームに二人を案内する。先ほどまでの軽い乗りの青年の姿が消え、堂々とした福祉専門職に見えることが祐子には不思議だった。たとえ駆け出しでも、職が自信と責任感を与えるのだろうかと、まだ経験したこともない職業への憧れと不安が顔を覗かせる。
南に開いた長い廊下を渡り、右に折れて北向きに張り出した棟に向かう。ホームの中は静まり返ったままで、行き交う人もない。いわれもなく不安が高まり、三人の足が早まる。
奥まった室のドアが開け放されているのが見えた。
急ぎ足でドアの前まで行くと、白衣姿の女性が出て来て天田の顔を見つめた。「様態が急変しました。もう危篤状態です」と告げる。
声と同時に三人の顔がこわばった。天田を先頭に静かに室に入る。
大きなベッドが室内の大部分を占めていた。三人で周りからベッドを取り囲み、横たわった小さな老女を見下ろす。室内には他に誰もいない。
老女は寝入ったまま身動きもしない。微かに上下する皺だらけの細い喉が、彼女の命を弱々しく主張していた。
「おばあちゃん」と、天田が呼び掛けても何の反応もない。微かな呼吸だけが不規則に続いている。
枕元に立った祐子が見下ろす老女は、まるで見覚えのない人だった。三年前の夏、元山神社の境内で、白髪を日に煌めかせてヴァイオリンを操っていた同じ老女とはとても思えなかった。
祐子の記憶にない、目を閉じた小さな顔は、今、萎んでしまった風船のようにユーモラスでグロテスクに見えた。微かに聞こえる息の音が不快だった。豊かだったはずの銀色の髪も三年の間に疎らになり、張りを失った頭皮が所々に露出していた。褐色に見えるくすんだ色の皮膚の上に、黒々とした染みが随所に浮かんでいる。
祐子は、老女の醜さがやり切れなかった。人はなぜ、こんな姿になってからも生きるのだろうと思ってしまう。腐ったタマネギの匂いのような、陰惨な臭気さえ漂ってくる。悲惨だった。
目を伏せてしまいたくなったとき、唐突に老女の目が開いた。不規則な息の音が一層高まる。
見開かれた老女の目は、祐子の目を見つめていた。黒く、漆黒の闇となった二つの目が祐子を見つめる。しかし、その目は何も訴えはしなかった。何の感情もなかった。無と化した両眼が、ただひたすらに祐子の視線を吸い込んでいく。
ホームに来るまでの自分の記憶が靄の中に霞んでいる。これまでわだかまっていた一切の思いが掻き消え、遠く遠く、暗黒の彼方へと吸い込まれていく。逆立ちになって闇の中を浮遊しているような、恍惚とした気分が祐子の下半身を満たした。濃密で豪奢な闇に全身が溶け込む。
「もっと、もっと」と、心の深奥でやるせないまでに無と化した闇を求めた。
濡れた股間から冷たい感情が立ち上がり、ゆっくりと身体を這い上がってくる。たまらず身悶えすると、剃り上げて一週間経った陰毛の先が、内股を鋭く突いた。陰毛の刺激で我に返る直前、喜びに震える老女の喘ぎを、祐子は確かに耳の底で聴いたと思った。
老女の不規則な呼吸がひときわ高まり、ヒーと長く尾を引いた。黒々と大きく見開いていた目が、見る見るうちに濁っていく。
あの暗黒の瞳は幻だったのかと、祐子は思った。食卓に上る鰺の干物のように、白茶けた目が眼下にあった。
「看護婦さん」と叫ぶ、天田の大声がすぐ近くで響いた。
「ご臨終です」
駆け付けた医師が老女の瞳孔にミニライトの光を当ててから言い、そっと瞼を下ろした。さっと看護婦が白布を広げ、老女の顔を覆った。
それで終わりだった。
消え入りそうに小さな遺骸に全員で頭を下げ、死との出会いに打ちひしがれて室を後にした。 |