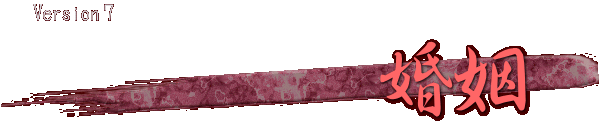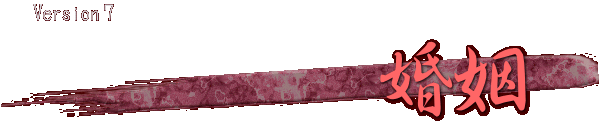時刻はとうに午後十一時を過ぎて、平日の歓楽街を飲み歩く人の流れも途絶えて久しかった。サロン・ペインのカウンターには祐子しか座っていない。カウンターの中でグラスを磨いていたチーフが、酒場に不似合いなミルクに口をつけた祐子に苦々しく声を掛けた。
「まるでMが座っているように見える。祐子、いっそのことマティニを飲みなさいよ」
「初めてこの店に来たとき、私にミルクを勧めたのはチーフよ」
冷やかしを待っていたように、すかさず祐子が答えた。長い髪がいらだたしそうに揺れる。
「十年前の話でしょう。祐子はまだ十五歳だった。私は二十五。Mは確か三十二歳だったわ」
遠くを見る目つきでチーフがしんみりした声で言った。祐子が気ぜわしく言葉を引き取る。
「Mはもう四十二歳になるわ。私はMが二十七歳の時に鉱山の町で知り合ったの。あのころのMは思い切り輝いていた」
祐子の言葉にチーフは応えない。気まずい沈黙がカウンターに落ち、二人の脳裏でMの記憶が渦巻いた。
「三年間は辛かったでしょうね」
突然、泣き出しそうな声でチーフが言った。言い出しかねていたことを先に言われてしまった祐子のいらだちが募る。無性に時刻が気に掛かり、振り返って壁の時計を見た。針は午前零時を回っていた。やっとMの出所の日が来たのだ。肩の力が抜け、ホールを掃除するモップの音が間近に聞こえた。
「たかが三年の刑務所暮らしでMが音を上げるはずがない。若い女囚を集めてスケベなことを教えているに違いないよ」
「あなたっ、なんてことを言うの」
フロアにモップをかけていた天田の陽気な声に、チーフが怖い声で応じた。
「天田さんの言うとおりだといいな。それなら安心できる」
すがるような声で祐子が応えた。
「大丈夫だよ、そうに決まってる。仮釈放にもならずに満期まで務めてくるんだ。相当ひどいことをしていたに相違ない」
「よしなさい。Mの悪口は許さないわ」
チーフがまた怖い顔で天田を睨み付けた。
「亭主よりMの方が大事なんだから、俺だって妬けるよ。祐子ちゃんもそう思うだろう」
同意を求める天田の言葉に、思わず祐子は笑ってしまった。何と言っても二人は似合いの夫婦だった。チーフを妻に選んだ天田の見識を見直すと共に、応じたチーフの勇気も立派だと思う。人の世もまんざら捨てたものではない。つかの間の温かさが心に満ちる。とにかく行動することだと祐子は確信する。
「ごちそうさま、もう行くわ」
明るい声で言って祐子が立ち上がった。
「行くと言ったって、Mの出所は朝の七時よ。今から出掛けると午前五時には着いてしまうわ」
チーフが怪訝な顔で言った。
「午前零時で刑期は終了したわ。Mは七時まで待ってくれないような気がするの。夜明け早々に刑務所を出て都会に行かれてしまったら、二度と会えないかも知れない」
厳しい表情で祐子が答えた。チーフの顔に不安がよぎる。
「そうね、裁判の時のMの態度は立派だったけど怖かったわ。あれっきり誰もMを見ていないのね。何度面会に行っても会ってくれないし、まるで私たちを避けているみたいだった」
震える声でチーフが事実を口にした。祐子の身体にも震えが伝わる。裁判所で胸を張って判決に聞き入る堂々としたMの姿が目の前に浮かび上がった。
「懲役三年に処す」
裁判長の重々しい声が最前列で傍聴していた祐子の全身を震わせた。前科のあるMに執行猶予はつかない。覚悟していた実刑判決だったが、やはり胸が締め付けられた。だが、Mは動じる風もない。静かに一礼して裁判長を見上げた。裁判所に言いたいことがあれば言いなさい、と言う裁判長の声に小さくうなずく。黒いワンピースを着た後ろ姿が大きく見えた。背筋を正した均整のとれた身体から静かな声が廷内に響いた。
「現金強奪グループの過激な行動にも関わらず、各施設の皆さんに負傷以外の重大な損傷がなかったことを率直に喜びます。しかし、グループ内の膨大な死者の責任と人格をどのように贖えばよいかを考えると暗澹とした気持ちになります。修太、如月、弥生、卯月、皐月、水無月、文月、葉月、長月、神無月、そしてオシショウと飛鳥。十二人の死者が裁かれることもなく彼岸にいます。生き残った私もピアニストも、睦月、霜月、極月の三人も、死者と同じ彼岸にいるしかないのです。裁判長、善悪を越えたところで芽生えた信仰を裁くことができないように、私の犯行への参加も裁けないでしょう。彼岸にそびえる無限のエネルギーの塔は、昇っていった者の責任と人格しか問わないのです。たかが懲役三年という社会の寛大な裁きには取り立てて言うことはありません。ただ、テロ組織に誘拐された私が、強いられて今回の犯行に荷担したとは決して思わないで欲しいのです。私は最後まで自分の責任と人格で行動したことを申し添えます」
懲役五年を求刑していた検察も実刑に満足し、量刑を不服として控訴することはなかった。Mも控訴しないで下獄した。再びオックスフォードに帰った祐子はイギリスでの生活を二年間延長した。光男と修太の死に続くMの不在を耐えきれる自信がなかったからだ。
「今朝Mを捕まえられなかったら二度と会えないような予感がするの」
つぶやくように言った祐子の言葉にチーフが大きくうなずく。
「そうね、私もそんな気がする。祐子、悪いけどすぐ迎えにいってよ」
急かすように言ったチーフの目を祐子が見つめた。不安そうな眼差しの底に、Mに捨て去られる恐怖にすくんでいる顔が映っていた。
「そんなことはないさ。出所前のらんちきパーテイで疲れ切って、Mが朝早く起きられる道理がない。ゆっくり行けばいいよ」
愉快そうに告げる天田の声が深刻な顔で見つめ合う二人の間に落ちた。緊張の糸が切れ、苦い笑いが祐子の口元に浮かぶ。チーフが天田を振り返って睨み付けた。祐子の目の前で夫婦の情愛が往復したような気がした。まだ実感したことがない感情だった。だが、Mも知らない世界だと思えば悪い気はしない。祐子は黙ってドアに向かい、二人に挨拶してからサロン・ペインを後にした。明かりの消えた看板灯の横に真っ赤なMG・Fが駐車してある。三年前にMが使っていた車だ。刑務所からの帰り道は、ぜひMにハンドルを預けて助手席に座っていたいものだと祐子は願った。
市から北へ、高速道路を乗り継いで五時間走った所にMの収監された刑務所はあった。インターチェンジを下りて四車線もあるバイパスを三十分ほど走った場所だ。全国的な都市化の波をもろに被り、周囲にはショッピングセンターやファーストフードの店まで進出している。開発が進む街の勢いに取り残されて見捨てられたように、先住者の刑務所は肩をすぼめてうずくまっていた。新興の住宅団地に取り囲まれた花火工場や養豚場のように違和感がある。祐子は改めて高い塀に沿って刑務所の回りを一周した。車で簡単に回りきってしまえるほど刑務所は狭い。古都の寺院の伽藍を思い出し、尼寺に引きこもってしまったMを想像してみた。意志して引きこもらない限り、社会と隔絶した生活を送るには悲しすぎるほどの狭さだ。しかしMは尼ではない。強いられてこの刑務所で三年間を暮らしてきたのだ。祐子の胸がまた熱くなってしまう。
三月中旬とはいえ、夜明け前の底冷えはきつい。フロントガラスの周囲が白く曇ってくる。MG・Fを止めたコンビニエンス・ストアの駐車場からは斜めに刑務所の正門が見通せた。門を隔てた四車線のバイパスをヘッドライトがまぶしく行き交う。思ったより交通量が多い。漆黒の空がほんのりと白み、ライトのまぶしさが気にならなくなったころ、東の空に日が昇った。朝日は刑務所の真っ黒のコンクリート建築の端から顔を出し、アスファルトの路面を赤く染め上げた。ちっぽけな太陽だった。横断歩道の先にそびえる巨大な鉄扉の隅で小さな潜り戸が開いた。黒い制服を着た刑務官に従って大柄の女性が出てくる。短い髪型だったが、端正な横顔と長く伸びた脚が祐子の目に飛び込んできた。慌てて車のドアを開けて冷たい地面に降り立つ。
「Mッ」
大声で道路の向こう側に呼び掛けた。横断歩道の信号はあいにく赤だ。行き来する車両が途切れる様子もない。もどかしく手を振ってみたが、門前に立ったMは応えようとしない。背中から朝日を浴びた真っ黒な人影が、全身で祐子を拒絶しているように見えた。
「Mッ」
もう一度かん高い声で叫んだ。黒い影が一瞬動揺したように揺れたが足早に歩き出す。信号が青に変わった。祐子は凄いスピードで駆け出し、四車線のバイパスを渡りきった。
「Mッ」
息を弾ませて三度目を呼び掛けると、二メートル前の後ろ姿がゆっくり振り返った。
「やっぱり来たのね。一人にはさせてくれないの」
三年振りに聞いた声は冷たかった。誰が面会に行っても会おうとはしなかったMだ。予期していた答えだった。
「私が来なければ、Mは黙って姿を消すわ。私たちの記憶を消してしまいたいMはいいけれど、消される私たちは耐えられない。置き去りにされるのはもう懲り懲りよ。ねえ、お願い。一緒に市に帰って。私はMを求めているの」
身体を振り絞って訴える祐子の言葉に見開かれたMの目が曇る。落ち着いた表情に苦悩が掠めた。
「祐子は、私が迷惑するとは思わないの」
刑務所前の寒い空気に乾いた声が落ちた。祐子の肩が震える。だが、ここで引き下がるわけにはいかない。Mを放してしまえば自分の生涯もなくなるような気がした。
「思うわ。でも、見捨てて欲しくないの」
祈るように祐子が言った。
「祐子はもう一人前の女よ。独りで十分生きられるわ。私も祐子と同じように独りで生きさせてもらいたいのよ」
断固とした声で答えたMが背を向けて歩き出す。
「逃がさないわよ。裸になってどこまでもついていく。これがMに学んだ私の生き方」
拒絶した背に叫んでアイボリーのコートとグリーンのワンピースのファスナーを下ろした。両手に力を込めて二枚の服を脱ぎ捨てる。白い裸身が朝日を浴びて真っ赤に染まった。陰毛を剃り上げた股間を冷気がなぶる。引き締まった裸身を躍らせて後ろ姿を追い、Mの背中にきつく抱き付く。振り切ろうとする胸元に両手を回して紺のスーツの上着をはぎ取る。スカートを膝まで引きずり下ろすとMの歩みが止まった。すかさず白いタートルネックのセーターの裾をつまんで力いっぱい引き上げた。Mはセーターで顔を隠したのっぺらぼうの裸身を晒す。刑務所の規則正しい過酷な暮らしに耐えた引き締まった身体だ。肌の白さが目にまぶしい。黒々とした陰毛が股間に燃え上がっていた。
「祐子ッ」
振り返ったMが感極まった声で祐子を呼んだ。膝まで下りたスカートが足元に落ちる。刑務所の正門から十メートルの所で、高い塀をバックに素っ裸の女が抱き合っている。行き交う車のクラクションの音が響き渡った。正門の潜り戸が開き、数人の刑務官が慌てて二人の方に駆け寄っていった。希望に満ちた祐子の目から喜びの涙がこぼれ落ちた。
「百歩譲ってもドーム館で祐子と暮らすわけにはいかないわ」
MG・Fの助手席で心地よく車の揺れに身をまかしている祐子の耳にMの声が響いた。
「Mは疲れているはずよ。落ち着くまでは一緒に暮らして欲しいの」
「私は疲れていない」
媚びるような祐子の頼みに、にべもなくMが答えた。
「だってMは、お金もないし職もない」
言ってしまってから祐子の頬が赤く染まった。Mが気にしたかと思って横顔をうかがう。真っ直ぐ前を見て運転するMの口元はほころんでいた。
「お金持ちの祐子が心配してくれるのはありがたいけれど、私はお金を持っているの。働いた分には見合わないけど、刑務所ではお金をくれるのよ。当座の心配は要らないわ」
「いくらあるの」
「三十万円もあるわ」
「一か月しか持たない」
「とにかく一か月持てばいいのよ。正直な気持ちを言うと、今でも市に戻りたくない」
「ごめんなさい」
「気持ちはどうあれ、私が市に戻ることを決めたんだから祐子が謝ることはないわ。とにかくアパートを探す。月五千円くらいの安い部屋がいいな。トイレも風呂も、キッチンだって共用で構わない。刑務所の雑居房で三年も暮らしたんだから十分すぎるくらいよ。個室が持てるのは大した出世よ」
楽しそうに話す横顔に見入った祐子の目がまん丸になる。小さく開いた口から溜息が漏れた。数回まばたきを繰り返すと涙がこぼれ落ちた。
「三年間は辛かったんでしょうね。ごめんなさい。私はMの気持ちを少しも考えていなかったわ」
「辛くなんかなかったわ」
ポツンと答えて首を振った。確かに辛い三年間だったとMは思う。毎日の暮らしのすべてが強制され監視されているのだ。人格さえ否定される。当然のことに自由はない。呼吸することだけが唯一、囚人に許された自由だった。その自由さえ奪われる者もいる。地獄より辛い所だ。
「そう、Mは心身共に鍛えてあるもの。股間の毛を剃ってしまえば勇気も湧くし、どんなところでも自分の責任と人格で生きられるわね」
祐子が啜り上げて邪気のないことを言った。Mは思わず笑ってしまう。刑務所で剃刀など持っていられるはずがない。鉄格子の中で隠匿物を疑われれば、それこそ毎日のように素っ裸にされ、尻の穴まで検査されるのだ。股間を剃るなど論外のことだった。裸にされることはあっても、勝手に裸になることなど許されない。自由はないのだ。だが、たわいない祐子の話が解放された自分を再確認させてくれる。うれしかった。
「そうだわ。アパート探しは天田さんに頼もう。ねえ、いいでしょう。月五千円の部屋なんて、不動産屋では見付からないわ」
祐子がはしゃいだ声で言って、バッグから携帯電話を取り出す。ケースワーカーの天田なら安アパートに詳しいはずだ。
「いいわ、お願いして。できれば今日中に入居したい」
答える声が弾んでいた。三年間、国の施設にホームステイしていたのだ。すぐにも自分の部屋が欲しいと思った。 |