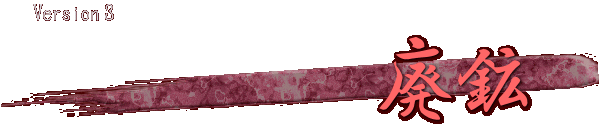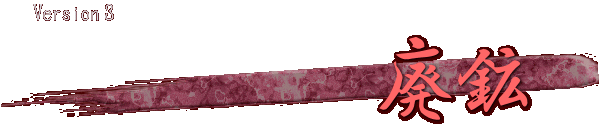「観光課の方はいませんか」
静まり返った昼休みの役場に、エネルギッシュな女性の声が響いた。
机の上にうつ伏して、うたた寝をしていた村木が顔を上げてカウンターを見る。黒いダウンジャケットを羽織った若い女が、にこやかに会釈をした。
「はい」と答え、村木は面倒くさそうにカウンターの前に立つ。
「初めまして。今度、町の観光パンフレットを請け負わせていただいた広告会社のMです」と言って、若い女が名刺を差し出す。
「はい、はい、ご苦労さんです」
眠そうな口調で応えた村木は、まだ三十歳になったばかりだった。
活力を失った町の空気が職員にまで伝わるのかと、Mはあきれながら返されるはずの名刺を待った。
「名刺を持っていませんのであしからず。僕が担当の村木です」
Mは拍子抜けして、手に持った名刺をカウンターの上に置いた。
職員に名刺を持たせない役場の姿勢が、この町の衰亡振りをうかがわせる。
鉱山で栄えたこの町の人口はかつて三万人を数えた。しかし今、町の人口が四千人にまで減ってしまっていることを、Mは出掛けに図書館で見た町村要覧で知っていた。
「精錬所跡に案内してくれますか」とMは言った。
唐突な申し入れだったが、名刺交換もないありさまでは、すぐ本題に入った方が手っ取り早いと思われたのだ。
「えっ、今からですか。まだ昼休み中ですよ。それに、車もない」
「もう少しで昼休みも終わります。私の車がありますから、ぜひ案内してください。この町で一番有名な所なのでしょう」
「ちょっと待ってください。課長の許可がなくては、出歩くわけに行きませんよ」
「昼休みだから、勝手に出歩けるのと違いますか」
いつになく強引な女が来たと村木は思った。たかが業者のくせに役場の職員をないがしろにしているとさえ思い、剣呑な気分にさえなってくる。
「自分勝手すぎますよ。あなたは観光パンフレットを請け負った業者の方なのでしょう。いくら役場相手だといっても、うちが依頼主に違いはないのだから、少しはこちらの都合を考えてくれても良いのではないですか」
語尾を呑み込むようにして言い終わるとすぐ、村木は何事もなかったように笑顔を浮かべ、さり気なくMの後ろに視線を移した。
頭越しに素通りした視線が気になり、振り返ったMの目に、自信に溢れた足取りで近付いて来る中年の男が見えた。
「こんにちわ」
村木の大声に視線を移すと、彼は男に最敬礼している。
にこやかな笑顔を浮かべた紺のスーツの男はMにちらっと視線を当て、軽く会釈をしてから村木に呼び掛ける。
「外からのお客さんに喜んでもらえるよう、十分取り計かってくださいよ」
「はい、助役さん」と村木がまた、最敬礼を返す。
去っていく男の背に、Mは慌てて「助役さん」と呼び掛ける。恰幅の良い男が振り返ってMの目を見つめた。
「私が外部の人間だと、なぜ分かったのですか」
「私はこの町の人の顔を、みんな知っています」
「本当ですか、四千人もいるのですよ」
「知っているのです。ところで、あなたは観光に来てくださったのですか」
「いいえ、いわゆる業者の一人です。町の観光パンフレットを作りに来ました」
「それは、ご苦労様です。大事な仕事ですから、よろしくお願いします。良いものを作っていただくためなら、何でも便宜を図りますよ」
「初対面の上、早速で申し訳ないのですが、お言葉通り便宜を図ってもらって差し支えないでしょうか」
「もちろん構いません。よろしくお願いします」
「ありがとうございます。実は、精錬所に案内して欲しいとお願いしていたところなのですが」
「閉鎖されて久しい施設に行っても仕方ないと思いますが、ぜひにと言うなら案内させていただきますよ」
「えっ、まさか助役さんが」
「いえ、申し訳ないのですが、私は予定が入っているので行けません。村木に案内させます。村木君、頼みましたよ」
「はい」
大きな声で村木が答え、助役にまた最敬礼した。急いでカウンターの外に出て、全身でMを案内する素振りを見せる。
あまりに早い態度の豹変振りに、思わず吹き出しそうになったMだったが、素知らぬ顔で村木の後に続いた。
背後から「良いものを作ってくださいよ」と助役の声がかかり、足を止めて振り返ると、明るい窓をバックにした大きな黒い影がさっと右手を振った。
村木は、先ほどまでの疲れ切った態度をがらりと変えた。
背中に注がれる助役の視線を意識して胸を張り、足早に歩く。そんな村木に追いすがるようにしてMは横に並び、階下へと続く階段を下りた。
「今、車を借りてきますから、ロビーでちょっと待っていてください」
玄関の自動ドアの前で立ち止まった村木がMに小声で言った。もはや助役の目に触れる心配がなくなったためか、再び疲れ切ったようなだるい口調に戻っている。
「いえ、先ほど言ったように私の車で結構です」
「そうはいきません。助役命令ですから、立派な車を借りてきますよ」
「申し訳ないけど、私は急いでいるんです。玄関のすぐ前に車があるのですから同乗してください」
立ち止まっている村木を促すように、Mはドアを開けて外へ出て行く。
「本当に強引な方ですね」と言いながら、仕方なく外に出て来た村木は寒風に肩をすくめた。
三月になったとはいえ、吹きつける風は肌を刺すように冷たい。
ダウンジャケットのファスナーを上げて先を歩くMが、無造作に赤い車のドアを開けた。途端に村木の顔がこわばる。大きくドアが開いた真っ赤な車に屋根はなかった。
オープンにしたユーノス・ロードスターにいち早く乗り込んだMが、村木を振り返って「どうぞ」と、いたずらっぽく笑う。
肩をすくめたまま寒風に吹かれる村木は、ニットのベストにサンダル履きのままだった。
「ちょっと待ってください。この季節にオープンなんですか。風邪をひきますよ」
「慣れれば、あなたも病みつきになるわ。雨の心配のないこの季節は、オープンが一番です。爽快ですよ」
「そんな、ちょっと待ってくださいよ。何か着てきますから」
大きなくしゃみをした村木は辺りを見回し、たまたまトラックから降り立った作業コートを着た男に駆け寄って行った。
「同級生が来てくれて助かりましたよ」
カーキ色のコートのファスナーを引き上げながら助手席に座った村木は、また大きく、くしゃみをした。構わずMはロードスターを発進させる。ひときわ激しく吹きつけた北風が二人の顔をなぶる。フロントガラスで鳴る風が轟々と凄まじい音を立てた。
「次の信号を左。山の方に入って行くんです」
大きくうなずいたMは、黄色に変わりかけた信号に向かってアクセルを踏み込む。タイヤがきしむ音が風の中に響き、一瞬、車体が左側に沈んだ。
「凄い運転ですね」
村木の震える声が風にかき消されていく。
車は家並みの立て込んだ商店街を抜け、細い舗装道路を山の中へと上って行く。しばらく走ると、急に軒を連ねた鉱山住宅が出現した。まさに突然現れたかのように、かつての殷賑さをしのばせることもない灰色の町が目の前に続いている。時折歯の抜けたような空き地があったり、新しいアパートがあったりして、死に絶えてしまったわけではない町の鼓動を、遠慮がちに訴えている。
今にも両側から崩れてくるような廃屋の並木を縫って、ロードスターはくねくねとカーブを曲がっていった。
赤錆びたレールだけが残る廃線となった鉄道の踏切を越え、黒く堂々とした鉄骨で組まれたアーチ橋の下をくぐった。切り立った崖が左右から迫る切り通しをタイヤを鳴らして鋭くカーブする。
突然視界が開け、目の前に深い渓谷が広がっていた。
Mは急に広々としたコンクリートの道路に出たことに驚いたが、渓谷沿いの路側帯のガードレールに寄せて車を止めた。エンジンを切ると静寂が訪れ、幾分弱まった寒風が耳元を冷たく掠めた。
眼前の深い渓谷に落ち込む切り立った山塊は、黒々と煤けた岩肌を露出したままだ。遥かに見上げても一切の緑がない。だが、よく見ると痛々しい岩肌に当てた包帯のように、白いコンクリートのベルトが幾筋も走っている。その上に盛った土に、貧相に植えられた草むらが寒々と見える。褐色の枯れ草は寒風に吹きさらされ、不規則に揺れ動いていた。
そんな満身創痍の山塊に張り付くようにして、不気味な鉄とコンクリートの怪異なフォルムで精錬所は存在していた。まるで、山塊を蝕む寄生虫のようだ。
峨々たる山には負けるが、それでも大きな丘ほどもある凶々しい建築物が、醜悪なペニスのように屹立した煙突を、誇らしく聳えさせている。この巨大な煙突の先から、数十年に渡って亜硫酸ガスが排出されたのだ。風に乗って谷筋を渡り、山肌を駆け上っていった毒ガスは、緑に恵まれた町の山々を無惨な禿げ山に変えてしまった。今はただ、昔の罪業を恥じるかのように静まり返り、廃墟は山裾にたたずんでいる。
Mはハンドルを握りしめたまま、じっと廃墟を見つめた。建築それ自体は何と形容したらいいのだろうか。それはまるで、無数の砲弾を浴びて沈没寸前でのたうち回る戦艦のようでもあったし、無数の鉄材と産業廃棄物で造形したオブジェのようでもあった。しかも奇妙な静寂が荒廃しきった全体を支配しているのだ。今も増殖をやめないガン細胞が発信する邪悪な意志さえ、見る者に伝わってくるような気がする。
Mは小さく身震いしてからドアを開け、路上に立った。
「ここが中心なのね」
渓谷沿いのガードレールへ2、3歩近寄ってMがつぶやいた。
「えっ、何の中心だって言うんですか」
Mのすぐ後ろに立った村木が大きな声を出した。
「この精錬所が、この町を作ってきたのでしょう」
「そんなの昔のことですよ。さっき助役さんが言ったとおり、精錬所はずっと前に閉鎖されてしまっているんです。もう精錬所でもない。ただの残骸ですよ。取り壊すお金がもったいないから残っているだけのものです。決して残しているわけではない」
「精錬所のことになると、やけに饒舌になるのね。きっと、今でもここが中心のままだって事じゃないかしら」
「そう思うのはあなたの勝手ですが、あなたにお願いするパンフレットには、精錬所の残骸など載せる必要はありません。町のパンフレットなんですから、町の意向には従ってもらいますよ」
「町を売り出すためには、すべてを知っておきたいだけよ。間違いがあったら困るでしょう」
Mは肩をすくめ、ガードレールから身を乗り出して渓谷の底をのぞき込んだ。
大きな岩の間を清澄な水が勢いよく流れている。耳を澄ますと風の音に混じって、ドウドウという水音も聞こえてくる。
「美しい流れね、怖いくらいに澄み切っている」
「水瀬川の源流ですからね。下流域の多くの人たちを含め、たくさんの命を養っている清流です。ぜひ紹介して欲しい自然の一つですよ」
誇らしく言い切る村木の声を背中に聞き、Mは図書館で読んだ鉱毒にまみれた同じ川のことを思いやった。
この清澄な流水がかつて、洪水の度に多量の鉱毒を流して多くの人を苦しめたのだ。しかし、眼下の水瀬川は鉱毒の記憶などは知らぬ顔で、自信に満ちて流れている。その流れは速く、川岸に立つ醜悪な精錬所の建築物を決して川面に写し出すことはなかった。
「村木、この寒いのに外で油を売っているのか」
二人の背後から遠く声がかかった。良く澄んだバリトンに振り返ると、道路を隔てた山際の山門の前に、ベレー帽を被った老人がたたずんでいる。
「何だ先生か。人聞きの悪い、仕事ですよ、仕事」
おどけた声で老人に答えた村木が、苦笑してMを振り返った。
「実は、あれが僕の住まい。あの人は高校の時の恩師なんです」
「え、住まいって」
Mが目を凝らして古ぼけた寺院を見ると、裏手に意外に新しいモルタルのアパートが見えた。
「僕は、あのアパートに住んでるんですよ。だから毎日精錬所と対面しているわけ。だから今さら、何の興味もない。ただのコンクリートと鉄の残骸としか見えませんね」
Mは一瞬言葉に詰まったが、さり気ない風を装って村木の言葉を肯定した。
「そうでしょうね。毎日見ていれば、ただの日常的な風景ですもの」
「そのとおりですよ。おまけに大家が恩師ときては毎日説教されているようで、精錬所どころではないんですよ」
対岸に張り付いた巨大な精錬所に背を向け、村木は大きな声で老人に話しかける。
「出版社の方が精錬所を見たいと言うのでお連れしたんですよ。これも仕事です。毎日見慣れている風景を見ても、僕はちっとも面白くありませんが、初めての人にはけっこうな迫力のようですよ」
「それが普通なんだよ。お前さんが不勉強なだけだ。あれほど全国を騒がせた鉱毒事件の中心なんだから、見てショックを受けるのが正常なんだよ」
「弱ったな、また説教ですか。帰ってからにしてくださいよ。せっかく出版社の方をお連れしたのに、弱っちゃうな。これだから来たくなかったんですよ」
村木は急にMを振り返って言葉をぶつけた。ここに来たくなかったとは初めて聞く言葉だったし、出版社の社員だと名乗った覚えもなかった。
「私が出版社の方だとは知らなかったわ」
「すみません。嘘をつくつもりはなかったんですけど、恩師に会ってつい動揺してしまったようです」
「今は大家さんなのでしょう。毎日動揺していなければならないわね。本当に精錬所どころではありませんね」
「そんな意地悪はやめてください。あなたのような美人と一緒にいるときに声をかけられたので、慌てたのが本心です。ごめんなさい」
媚びるように村木が言うと、Mは当然だと言いたげに胸を張って答えた。
「別に謝らなくても構いません」
「あなたは本当に自信たっぷりな人ですね」
「能力と自信がなければ、この世界は渡っていけないわ」
きっちりと言い切ったMの言葉で気まずい沈黙が訪れそうになったとき、道の向こうからまた老人が声をかけてきた。
「せっかくここまで来たのだから、ちょっと寄っていきなさい」
「毎日帰って来るのにせっかく来たもないもんだ。きっとMさんに言ってるんですよ。どうします。お茶を飲んでいきますか」
村木がMの顔をのぞき込んで尋ねた。
「あなたの恩師で大家さんのお年寄りに誘われたのだから、お寄りしないわけにはいかないでしょう」
二人は冷たい風が吹き抜ける広い道路を横断して山門をくぐり、老人に導かれるまま寺院の横手へと回った。間近に見る寺院は古ぼけてはいたが、結構立派で大きな寺構えを見せている。やはりこの町のかつての栄華が、寺の構えにまで色濃く反映しているに違いなかった。
小さな潜り戸から屋内に入り、外見からは不釣り合いなほど調度の整った洋室へと導かれた。ロココ風の布張りの椅子とテーブルを配した部屋の壁面は書棚が占め、隅に立て掛けられた黒く大きな楽器ケースが異彩を放っている。
「この町は初めてなのですか」
ゆったりとした布張りの椅子に深々と座って、老人が話しかける。
「僕はお茶を入れてきましょう」
勝手知った仕事を引き受けるように言って、村木が奥のドアに消えた。
「この先の観光地へ行くときに、何回か通り過ぎたことはありますが、町の中までお邪魔したのは初めてです」
「まあ、普通の人は皆、あなたと同じですよ。わざわざバイパスを降りて、ひなびた町を訪ねる物好きも多くはいません」
「初めて町に入ったのですが、やはり鉱山の影響が未だに強く残っていると感じました。私は町の観光パンフレットの制作を頼まれた広告会社のものなのですが、鉱山の扱いについて迷ってしまったんです。どうしても避けては通れないなって感じがしてしまうのです。けれど、村木さんを初め、町の人は、あまり鉱山に触れたくないようなんですね。あなたは村木さんの恩師だとお聞きしたので、教育者として鉱山のことをどう思っているか聞かせて欲しいのです。初対面で申し訳ないのですが、お寺に招かれたりすると、これもご縁のような気がしてしまいました」
「パンフレットの制作のために見えたのですか。それはご苦労様です。でも、鉱山のことはそんなに深刻に考えなくとも良いと思いますよ。誰だって知っていることですから、隠すことも宣伝することもない。ただ存在しているだけのものです。たとえ精錬所の残骸が残ろうが壊れようが、山に緑が戻ろうが戻るまいが、鉱山は歴史の中に存在し続けているのですよ」
淡々と語る老人の言葉にもMは、この町の疲労を感じてしまう。鉱毒にまつわる先入観が強すぎるのだろうとMは思った。
「ご住職の法話を聞いているような気分になってしまいました。学校では何を教えていたのですか」
年長者に対して礼を失した物言いだとは思ったが、あまりにも哲学的な答えが不満だったので、つい踏み込んで聞いてしまった。
「なるほど、坊主の説教に聞こえてしまいましたか。年は取りたくないものです。私は十年ほど前まで、この町の高校で美術と音楽を教えていたのですよ」
「えっ」
思わずMの口元から驚きの声が上がる。
「驚かれても仕方ないが、芸術を教えるのが本職なんです。住職をしていた父が死んだときから、坊主も引き受けるようになったんですよ」
「それでチェロが置いてあるのですね」
「そう、そうなんです」
今まで思慮深そうに構えていた僧侶の顔が崩れ、少年のように無邪気な笑顔がこぼれた。
「今でもお弾きになるんですか」
「弾きますとも。退職教員が集まって弦楽五重奏団を作っているのです。私はそこのコンサートマスターですよ」
誇らかに話す老人の顔は、既にアーチストの自信が満ちていた。
「何を演奏なさるのですか」
「モーツァルトです」
胸を張って答えた。
「素敵ですね。ぜひ聴かせて頂きたいわ」
「暖かくなったら演奏会を開きます。プログラムは弦楽五重奏曲第四番ト短調です。ぜひおいでください」
老人の顔がうれしさの中に埋もれた。
その時唐突に、入り口のドアがノックされた。
「恩師。お邪魔しますよ」
声と同時にドアが開き、紺のマウンテンパーカーの前をはだけた、がっしりとした体格の男が入って来た。パーカーの下は白のTシャツ一枚で、色のさめたブラックジーンズを穿いている。ジーンズの所々が黒い土で汚れていた。全身から外の冷気と、男の臭気を漂わせている。
「何だ陶芸屋か。つい先日湯飲みセットをもらったばかりだろう。しばらく注文はないよ」
いつの間にか僧侶の顔に戻った老人が、つまらなそうに応えた。
「作品の売り込みじゃないですよ。緑化屋の娘が、またいなくなったそうです。今、分校から連絡があったところなんです。これから捜しに行くのですが、一緒に行ってもらえないかと思ってお願いに来たんです」
「そうか、またか。困ったな、緑化屋は山に入ってるんだろう」
「当然ですよ。朝からヘリコプターに乗っているはずです」
「陶芸屋が一人で行っても、あの子はいうことを聞かないかも知れないな。一緒に行ってみるか」
「お願いしますよ。どうせ元山鉱の廃墟の辺りにいるんでしょうが、恩師が一緒なら素直に帰ってくれるでしょう」
「じゃあ行くか」と言って立ち上がった老人が、Mに視線を落とした。
「大変申し訳ないが、これから人捜しに行って来ますよ。この陶芸屋のせがれの同級生で、小学校六年生の娘が学校からいなくなってしまったのです。都会から赴任して来た緑化技師の娘なんだが、かわいそうに自閉症なのです。どういうわけか、年寄りの私には安心できるらしい。なに、いる所は見当が付いているから、それほど心配はないのですよ」
「私もお手伝いしましょうか」
「いや、あなたはいい。町の者でします」
きつい視線でMを見下ろして、陶芸屋が短く言い放った。
「よそ者が行くと足手まといって事かしら」
「そういうことです」
冷たい声で言い切った陶芸屋は、口をへの字に引き締める。声とは裏腹に、Mを見つめる視線の底で熱い炎が揺れた。
Mの背筋をむず痒い感情が走っていった。
「お待たせしました」
のんきな声が響き、村木が奥のドアから湯飲みを載せた蒔絵の盆を持って入って来た。
「あっ、先輩、こんにちは。先輩の分も入れて来ましょうか」
Mを見つめる陶芸屋に明るい声で呼び掛ける。
「お茶くみは役所の中だけにしておけ」
にべもなく拒絶された村木の顔が赤く染まった。
「僕は役所でお茶くみなんかしてませんよ。四月になれば主任になるんですから、もう上級職員ですよ。先輩こそ、もっと売れる陶芸を工夫して、町おこしに貢献すべきじゃないですか。芸術家ぶっていちゃ敷居が高くなるばかりですよ」
「お前に説教されるゆえんはない。小役人のくせに、かわいこちゃんを連れていちゃついてるから町が変わらないんだ。早く帰って町のための仕事をしろ」
Mは、きっとなって陶芸屋の顔を睨み付けた。
「私はかわいこちゃんという名ではありません。Mと言います。あなたはどなたですか」
「俺は陶芸屋だ」
動じる風もなく答える。
刺々しくなった雰囲気の中で、老人が取りなすように間に入った。
「村木。私は陶芸屋と一緒に緑化屋の娘を探しに行くから、折角入れたお茶をMさんに飲んでもらってから帰りなさい。Mさんも気を悪くしないでください」
「いえ、慣れていますから」
Mが応えると、老人と陶芸屋は連れ立って外に出て行った。
「チッ」と舌打ちする陶芸屋の声が、ドア越しに聞こえた。
「何て人かしら」
Mが独り言をいうと、盆をテーブルに置いて向かいの椅子に座った村木がぼそっと言った。
「先輩はMさんを好きになったんだ」
「えっ」
Mはびっくりしたような声を出したが、本当に驚いたわけではない。ついさっき、瞳の底まで踏み込んできた陶芸屋の熱い視線が脳裏に浮かぶ。村木の言葉を裏付ける予感がなかったとはいえなかった。
「陽子さんの時とまったく同じなんですよ。先輩は不器用ですからね。陽子さんは五年ほど前に離婚して、町を出て行った先輩の奥さんなんです。この町の人で同い年。ずっと幼なじみだったけど、先輩はプロポーズするまで辛く当たっていたんです。愛情の裏返しってやつですよ。結婚してからも凄い。陽子さんを素っ裸にして縛り上げ、外にも出さなかったといいます。愛情が激しすぎるんですよ。きっと先輩は、Mさんに会って陽子さんを思い出したに違いないんだ」
村木の話を聞くMの目が怪しく輝き出す。じっと村木の顔を見つめて低い声で応えた。
「そう。村木さんの推測どおりなら、私も陶芸屋に素っ裸にされて縛り上げられるのね」
村木の顔が真っ赤になった。
「うわさですよ、ただのうわさ。別にMさんを驚かすつもりはないですよ。真に受けてしまっては話にもならない」
頬を真っ赤に染めて抗弁する村木がおかしくて、Mは思わず笑ってしまった。
「何がおかしいのですか」
「いえ、思い出し笑い。村木さんってかわいいのね」
村木の頬が一層赤く染まった。
Mは楽しい気分で蒔絵の盆に手を伸ばし、冷えた茶碗を取った。
不思議な茶碗だった。ほとんど黒にしか見えない地肌に厚めの釉がかかり、所々が青みを帯びた鉄色に光る手焼きの茶碗だ。手に馴染む土の温かさが優れた陶工の技を感じさせる。Mは手に取ったまま、しばし見とれてしまった。
「その茶碗、気に入りましたか。先輩の作品ですよ」
目を上げると、村木がにこにこと笑っている。
「へー、そうなの。陶芸屋はアーチストだったのね」
「いや、幾つも作らないし、値が高いから売れないんですよ。気が向いたら、観光パンフレットに取り上げてやってください」
「もちろん取り上げるわ。この町の宝よ」
村木が声を上げて笑った。Mもつられて笑い、ひとときこの町と交流できたと、幸せな気分になった。
Mの好みにぴったり合った陶器が手の中にある。地肌の温もりから不意に、陶芸屋の熱い瞳と傲慢な態度が伝わってきた。ぽっと頬が赤く染まり、Mは村木に気取られないように話題を変えた。
「村木さんは、緑化屋さんのことも知っているの」
「知ってますよ。国の技官なんです。しかも高級官僚。禿げ山を緑にするために志願して来たそうです。もちろん都会の人で単身赴任なんですが、去年から自閉症の娘さんを呼び寄せて一緒に住んでいます。ずいぶん仕事熱心な人で、町が気に入ったみたいですよ。先輩と仲がいいんです。どちらもやもめの子連れ狼ですから、よく一緒に酒を飲んでいますよ」
「狼みたいに飢えているってこと」
「いや、二人とも個性が強すぎるという意味です。正直、怖いですよ」
「あなたは狼ではないの」
「からかわないでくださいよ。こんな山の中の寺で二人きりなんですから。狼になりたくなるかも知れない」
慌てた表情の村木が、つい本音をはいてしまう。
「狼になって見れば」
あっけなく言ってのけたMの目が妖艶に光ったように、村木には見えた。
「弱ったなあ。Mさんは意地悪ですよ。僕は先輩たちと違って気が弱いんですから」
「そう、私は意地悪よ。陶芸屋さんや緑化屋さんと同じくらい、私は村木さんのことが好きになったわ」
Mの低い声が村木を挑発した。
村木が唾を飲み込む音が聞こえた。
傲慢な陶芸屋を誘い込む前のトレーニングにちょうどよいと思い、Mは大きく開いた瞳で村木の視線を捉えたまま放さなかった。
村木の頬が少しずつ赤く染まっていく。固く勃起していくペニスを意識した村木は、苦しそうにまばたきしてから目を伏せてしまった。
目の底に残ったMは輝くほどの壮烈な美しさに満ち、静かに椅子から立ち上がるところだった。
静まり返った部屋に村木の早い呼吸音が響き、Mが羽織っていたダウンジャケットを脱ぐ衣擦れの音がした。
外は冷たい風が渡り、禿げ山に植え付けられた草むらの上でびょうびょうと寒そうに鳴った。
|