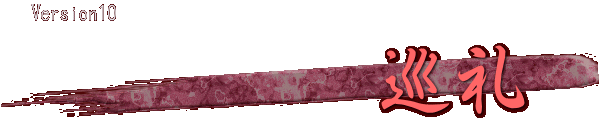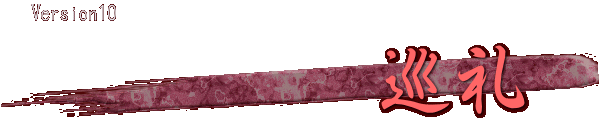僕は進太、十五歳になります。三月に中学校を卒業しましたが、まだ進路は決めていません。いわゆる無業者です。
市の辺境に位置する山地の独り暮らしは、切なくなるほどさみしい。十年間を一緒に暮らした、Mのにおいが染みついた蔵屋敷も広すぎます。
何よりもまだ、Mがいなくなった事実を受け入れられずに戸惑っているのが現実です。明日の朝になれば、Mがフッと帰って来るような気がして、日々が過ぎていきます。
そんな僕を心配して、市街地に住んでいるテキスタイルデザイナーの祐子が、二日おきに食材や日用品を届けに来ます。その度に祐子は、早く進学先を決めろと言って説教します。説教は必ず、Mの思い出話に続いていきます。Mの容姿の美しさから始まって、他者を思いやる優しさに行き着く賛美は、自分自身の責任と人格で自立して生きるヒロインを羨望することで完了します。
三十年近くMの生き方を見続けてきた祐子には、養子の僕の軟弱な態度が我慢ならないのでしょう。まるで、父の偉業を讃える母の役割を演じているような口振りなのです。僕の目には、Mの子分としか見えなかった祐子に、母親役を演じられては、たまったものではありません。Mがいなくなった後、茫然自失の体をさらけ出したのは、他ならぬ祐子だったのです。今もなお、生ける屍のように、無気力に暮らしています。三十七歳の年齢を笠に着て、僕に憂さ晴らしをしているに過ぎません。でも、Mの不在を耐えきれずにいる、祐子の気持ちは理解できます。
僕だって、所在なくMの帰りを待つ日々が耐えられません。しかし、僕は祐子のようにはなりたくない。たとえ祐子の目に、一人で進路を決めかねている僕の姿が、同類のように映ったとしても、僕は祐子の同類ではない。Mの不在にたじろぐことなく、Mと一緒に生きる道を捜し出したいのです。
あれこれと、考え続ける時間だけが、無為な暮らしの上に積もっていきます。
考えが行き詰まると市へ出掛け、サロン・ペインを訪ねます。
サロン・ペインは酒を飲ませる店ですが、店主のチーフがおいしいレモンスカッシュで僕を迎えてくれるのです。
チーフもMの子分のような女性ですが、本人はMの愛人のつもりでいるようです。ご主人の天田さんの前で、Mへの求愛の言葉を平気で口にします。きっと、天田さんの嫉妬心をくすぐり、いつも優位に立っていたいからなのでしょう。けれど天田さんは、同性への愛なんて、いっこうに気にしません。チーフを熱愛した自信が、彼のおおらかな性格を育んでいったと、Mが話していました。
天田さんは、Mが結婚したピアニストの、高校時代の同級生です。都会の大学を卒業し、市に戻ってきて市役所に勤めています。大の子供好きで、幼いころからサロン・ペインに出入りしていた僕を、とてもかわいがってくれました。小学二年生のとき、僕がMの養子になって山地の蔵屋敷に引き取られた後は疎遠になりましたが、刑務所で自殺してしまったピアニストの戸籍上の子になった僕を、ずっと見守っていたと言って自慢します。どう考えても滑稽な自慢ですが、開けっぴろげで恩着せがましくない態度が憎めません。最近は、僕のことを大人と認めてくれているようで、好んで性的な話題を持ち出します。露骨な話に戸惑う僕を、うれしそうな顔で見ているのです。
一月前の、桜の花が散り始めたころ、天田さんとチーフが山地の蔵屋敷を訪ねてきてくれました。
おいしい手作りの料理と酒を庭に並べ、僕を慰めるための花見の宴が始まりました。その席で、天田さんは、Mの性を肴にして酒に酔ったのです。「Mは、娼婦みたいにセックスが好きな変態女だった」と、あけすけに僕に告げました。横で聞いていたチーフは怒り狂いました。僕も仰天し、むっとしました。しかし、天田さんの話しぶりには、Mを貶めようとする悪意は感じられません。ありのままのMを愛でているような口調でした。
衝撃を受けた僕も、遠く去っていったと思っていたMが、急に身近に感じられたような気がしたものです。でも、正直言って面食らいました。祐子の目に映ったMの対局に天田さんのMがいます。そして、チーフが愛人として慕うMまでいるのです。一瞬、頭が混乱してしまいました。
目をつむると、僕の養母として毅然として立つMの姿が浮かび上がりました。そのMの背に、折に触れて逃げ込んでいった僕の後ろ姿が見えます。これまで見えなかった画面が見えたとき、動じようとしなかったMのイメージがぼやけていました。
この半年間、だれを待っていたのか分からなくなってしまいました。僕が待ち続けていたMは、一体どんな姿をしていたのでしょう。心の中が空っぽになり、情けなさが身に染みました。
僕は進学をやめます。
しょせん一人で生きなければならないのだとしたら、悔いだけは残したくないと決意したのです。
昨夜、Mに手紙を書きました。出すあてのない手紙ですが、僕の気持ちを整理してみたかったのです。
前略
Mがいなくなってから六か月が過ぎました。
初めての独り暮らしにも、ようやく慣れたようです。毎朝六時半に起き、ご飯を炊いて味噌汁を作ります。昼にはハムトーストと生野菜。ミルクコーヒーとオレンジも欠かしません。夕食には、午後のうちに下拵えをした、フィッシュやミートのメインデッシュが食卓を飾ります。料理の腕は、すでにMを越えましたよ。でも、蔵屋敷の大きなテーブルで食べる、ひとりぽっちの食事は味気ない。Mが一緒にいてくれたらと、食事の度に思います。そして、Mが話してくれた独り暮らしの時代を思いやってみるのです。
僕の知らない若々しいMがいます。完璧にひとりぽっちの、空虚な寂しさが伝わってきます。同じひとりぽっちでも、僕には側にいて欲しいと熱望するMがいるのに、Mにはだれもいなかったのですね。漠とした人恋しさに惑う姿を想像すると、やり切れなくなります。恐らくMは、心の隅にどうしようもない感情の吹き溜まりを抱えていたのでしょう。その大きさはともかくとして、僕の心の中にも吹き溜まりがあります。焦りや怒り、欲望や憎悪、そして堪らない悲しさが風に舞い、渦を巻いています。その吹き溜まりは、成長に応じて大きくなっていくような気がします。やがて等身大になり、身体を突き破って溢れ出すかと思うと、本当に怖い。
なぜMが、僕をおいて出ていってしまったか、問いたいとは思いませんし、責める気持ちも失せました。ただ、Mが僕に話してくれた物語が、日を追って胸の中で膨らんでいきます。
家を出る運命に追い立てられるように、身を持って体験してきた事実を、Mは時をたどって話してくれました。初めて聞くMの歴史を、僕は真剣に聴いたのです。そこには、思いもしなかった世界が大きく広がっていました。僕もいつしか、そんな世界の中に踏み出していかなければならないのかと思い、全身に鳥肌が立ったことを覚えています。
Mが語ってくれた様々な事実を、僕はひそかに「Mの物語」と呼びました。その長い物語が終わった十一月の朝、去年と同様、初氷が張りましたね。市へ行くと言って出掛けたMは、そのまま戻ってきませんでした。一人で山地に取り残された僕は、「物語」を何度も反芻してみました。
最近になってやっと、事実だけを見据えてきたMの生き方が、うっすらと見えて来たような気がします。だから、僕は写真家になろうと決意しました。
コントロールできない感情の吹き溜まりを、レンズを通してフィルムの上に対象化したい。事実を表現することで、身体から流れ出てしまう感情を凝縮させたいのです。
Mに見捨てられて、一人で生きていく僕にとって、カメラは最大の武器になると思います。けれど、当面カメラは要りません。何よりも、事実を見極める視点が欲しいのです。
僕は、明日から旅に出ます。
写真を撮る目で「Mの物語」をたどろうと思っています。これまでMが出会ってきた人たちが、Mをどのように理解していたかを聞いて歩きます。物語を実際に検証し、Mを捜し出す旅です。
天田さんに聞いたショッキングなMの姿。異常な性にまみれ、ひたすら官能を追い求めたという、もう一つのMの素顔に直面する勇気もあります。
これまで知らなかったMに会えるようで、いまから胸が躍ります。旅の途中で、現実にMと会えるかも知れませんね。楽しみにしています。
くれぐれもご自愛ください。進太 |